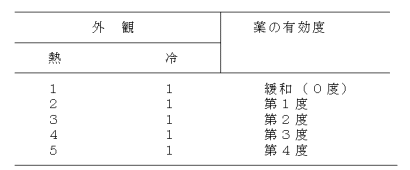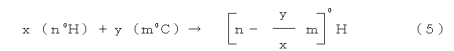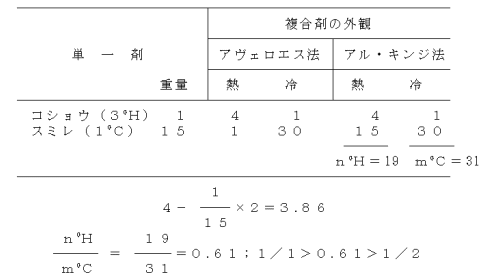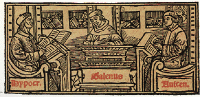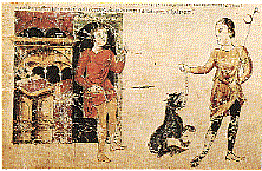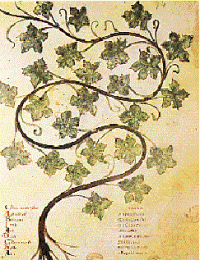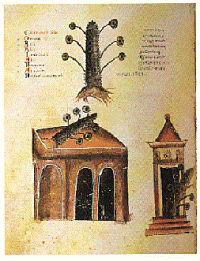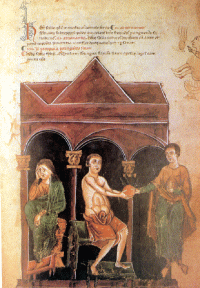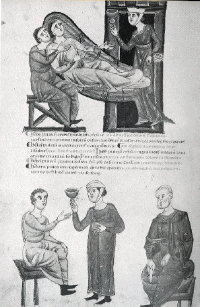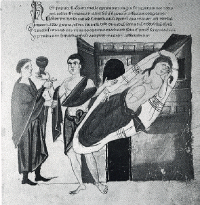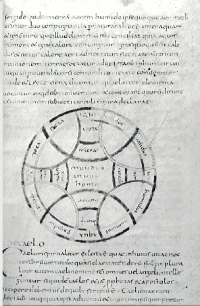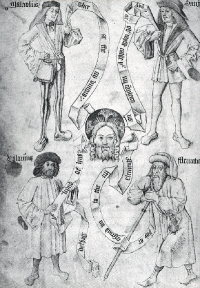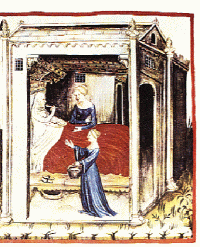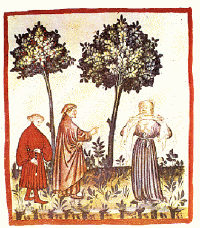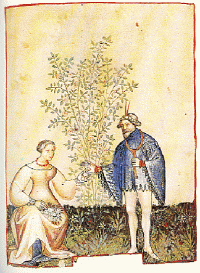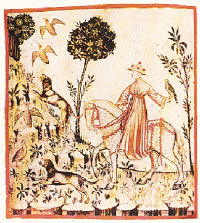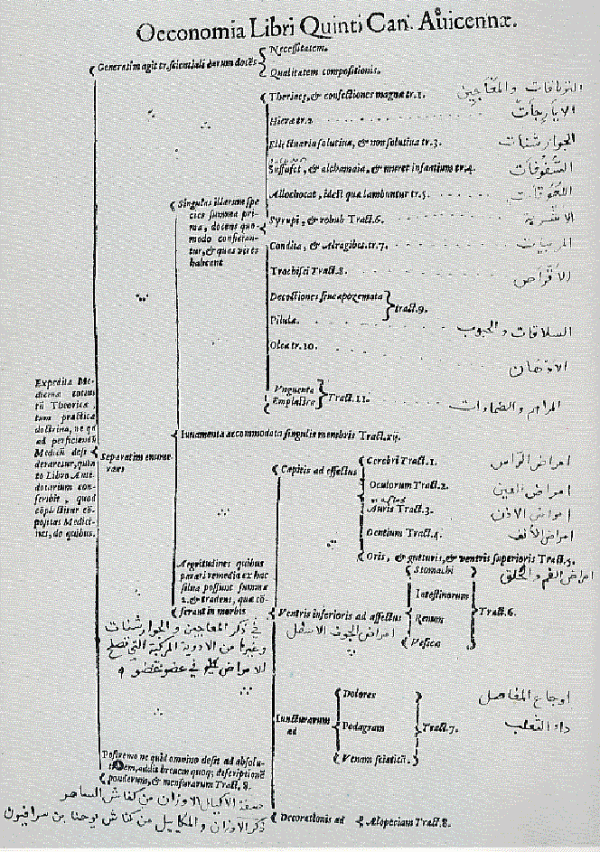|
ガ レ ノ ス の 体 系
ペルガモンのガレノスは、古代の医学を統合し有終の美を飾った栄光の人で、200年に人生を終えるまで200以上の論文を残している。その大半は専門的な医学の領域、たとえば解剖学、生理学、病理学、衛生学、薬物学の分野におよんでいる。ガレノスの著作は非常に多く相当な時間、たとえば4〜5年ほどかけないと修得できない。ガレノスは人生の終焉に向けて自ら体系化しようと努めたが、著述家としての活動範囲が広く、そのために混乱して自己の業績をまとめることができなかった。ガレノスの死後、著作の統一はかなり難しい仕事であった。医学生用に4年間の一貫したカリキュラムを提供するために、数世紀にわたる活動がはじまった。アレキサンドリアは642年にアラブが征服するまで、ヘレニズム時代とビザンチン帝国の初期数世紀の間、地中海の知識センターとして繁栄した。ここでガレノスに関する知識は、ほぼ標準化することに成功した。4世紀の第2半期にガレノスの著作を収集することができた。収集した蔵書目録は当時の医療人にとって、欠くことのできないものと考えられた。巻数は16巻で4年間の医学教育カリキュラムで修得できるように、大きく4群に分類し管理した。1〜4巻は序論で、5〜8巻は詳細な生理学の研究、第3部は9〜14巻で病理学、第4部は治療と衛生学である。フナイン・イブン・イスハクは、アレキサンドリア医学派のガレノス注解書を世に送りだした。アレキサンドリアの医学生はガレノスの16巻の著作だけを読んで勉強した。通常医学生は私が提示した上記リストの順に勉強に取り組んだ。
今日、キリスト教の修道士がスコレ(skhole)と称する教育施設に集まって、古代の学者が正典とした書籍を研究するが、医学生もそのように毎日顔を会わせて同じ方法でガレノスの著作を読みかつ解釈したようだ。これ以外のガレノスの著書についても、今日、私たちの仲間が先人たちの注解書を研究するのと同ように、当時の学生も一人で読むか、前記の研究にしたがって学習したらしい。
こうした学術活動によってやがて『アレキサンドリア要約書』として、ラテン語版のガレノス著作集の要約書・注解書が発行されるに至った。7世紀にむかって、16巻のガレノス医学の総集篇(総合医学入門書)が組れた。本書はローマ化したヨーロッパで医学入門書として知られる。私見だが、これはアレキサンドリアのヨハネと一緒に仕事をした医師団が整理したものと思われる。この重要な要約書は中世医学の主要な教義を網羅している。ビザンチン、アラブ、ユダヤ、ラテンの医学思想を理解するうえで、現存するもっとも重要な書籍である。
それではヨハネの入門書に書かれた医学の基本理念、すなわち本書の構成と一般的治療、とくに薬物学の役割について考察してみよう。「医学は理論と実践の二つに分類できる」という文章ではじまる。理論の部は三つに分類される。自然現象の観察、不自然な現象の凝視、不自然が自然になる現象の考察がその3項目である。疾病、健康、中庸に関する科学は、この3項目に該当する要素、原因、外観が基本である。これを別の観点からみれば、医学は理論と実践の二つに区分され、理論医学は自然、不自然(疾病)、自然でない中庸に関する調査・研究の3分野に大別される。これらの適用の仕方によっては健康が増進するし、また疾病が起こる。
第1章は「生理学」、第2章は「病理学」として知られ、第3章は「治療」と呼ばれている。ガレノスの時代では治療が両刃の剣であると考えられていた。簡単で必ずよくなるという治療法はなかった。栄養法、薬物療法、外科療法は活用の方法により健康や疾病の原因になった。したがって、これらの治療法は適用によっては、健康や疾病の生産者ともいえるだろう。
ガ レ ノ ス の 体 系 に み る 薬
ガレノスの体系における治療術を詳細に調べてみよう。現代ロマンス語の「Therapy(治療)」はギリシャ語のtherapeiaに由来し、神の祭儀における「奉仕」や「世話」という宗教的意味が語源らしい。その後、拡大解釈されて財産や人に対する奉仕や世話を意味するようになった。ギリシャ語の
therapainaは家の使用人や奴隷のことを指し、結局は「医療での介護・看護・奉仕・処置」を表わす言葉になった。初期のtherapeiaの定義は「処置」ではなく「世話」で、技術上とか医療上のことでなく、もっと人間的で宗教的な世話の意味であった。同じ語義の変化がラテン語でも起った。ラテン語のcuraは世話や勤勉(incuriaが反対語)の意味であったが、その後ギリシャ語の影響で
curatio(世話)が医療処置を表わすようになった。この変化にもかかわらずギリシャ語のtherapeiaとラテン語のcuratioは、当初の文化的性質や宗教的性質を失わずに残った。ギリシャと古代ローマの医師にとって疾病はいつも自然の混乱であり、厚い信仰や崇拝する姿勢以外に替わるものがない時代では、自然が究極的な概念(古代医学の「生理学上の信仰」とか「生理学上の信心」)を造りあげていた。
最終的には公正な立場から、古代療法の宗教的な意義に言及しなければならない。ヒポクラテスが健康について具体的に整然と解説したのを思いだすべきである。健康は天然物における一つの形式要素ないしは形式特性であった。ギリシャ人にとって健康は自然のなかに存在するもので、天から授かった自然な性質であった。したがって、正確な言葉は天賦の性質(diathesis
kata
physin)である。ヨハネの入門書に書かれているが、健康とは生理的に自然な状態である。健康は天与のフュシス(自然)の特性である。人類は自然だから健康である。この考えは現代人にもわかりやすいのだが、私たちとはまだ数マイルの隔りがある。私たちにとって健康は実際の資産であるよりも、理想的な概念に近い。ギリシャ思想の健康は抽象的な性質で、最終的には神学に帰するとされている。逆に疾病は「脱自然」か「自然の秩序の変容」と考えられる。疾病には超自然的な規則や反自然的な状態も入る。疾病は自然の異常(para
physin)である。私たちはヨハネの入門書という短編を読んだ。現代の医師は疾病がそれほどでなければ、健康と同ように自然なことだと思い、また日常会話で「疾病の自然史」といった言葉を使っているが、古代や中世の医家が疾病を超自然的あるいは反自然的な特性だと考えたのが不思議に思えるほどである。スコラ哲学者は超自然、反自然、神秘的自然をはっきりと区別した。これらは自然の秩序を超えるという意味ではまったく一致するが、同一の言葉ではない。この意味で古代思考では疾病は鬼神学的あるいは神学的な性質をもっていた。
一方、治療は健康状態の回復が目的である。この目的を達成するためには
疾病を発症させる過程とまったく逆の道を辿らねばならない。疾病とは自然な状態や生理状態から、反生理的ないし反自然的な状態への移行だとすれば、
治療は失った生理状態を回復させることが目的でなければならない。治療の
目的は自然の秩序を再構築することだが、治療もまた超自然的な行為である。いま、この過程を解説するために、なぜ宗教用語が使われたか、その理由を調べてみよう。疾病の内部やその間隙に優れた力が発生すれば、論理的に治療は宗教用語の解明と関連するに違いない。これがアスクレピオス神殿で催眠儀式を行う夢判断的なギリシャ医学に隠された思想であった。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教など中世の偉大な一神教は、繰り返して疾病の原因が罪にあると
解釈した。信仰により疾病をさけようとした理由がここにある。西暦の初期に一番規律が厳格なユダヤのキリスト教徒の一派が「therapeuts」の名を選んだという説は、まだ認められていない。
薬 と 治 療
薬物学は古典的治療や近代治療学の基礎である。繰り返すが、現代の視点で古代の薬に関する考えを推定するのはさけるべきである。『イリアス』に登場する古代ギリシ語のpharmacon(薬)は、超自然状態を無力化し自然の神聖な秩序を回復する「魔術薬」であった。薬はその本質のなかに「力」を失った身体をもとの自然な秩序(生理の調和)に回復させる力をもっている。
この自然と超自然の二重性はヒポクラテス全集で明らかにされ、薬とは「治療薬」や「浄化薬」のことを指していた。一番典型的なヒポクラテス薬は下剤である。その理由は下剤が古代宗教史の長年の伝統である「浄化」を起こすからである。
「medicament(薬)」も重要な同義語一つである。こうした語義上の変革は、すでに調査した言葉と同じであった。動詞の「iatreuo」は治療する(cure)ばかりでなく、看護する(care)の意味もある。動詞の「iaomai」はiamaに由来し、同じ語源で同一の意味で「治療する(remedy,medicine)」を表わす。医師(
physician、doctor)は診断者でなく治療者であり、もっとも典型的な薬は治療する力をもつ天然物や薬である。古典医学では医師は正式に薬剤師として定められている。もう一度実践医学についてヨハネの入門書を参照すると、最後の3行(外科医に関する部文)以外は、薬物療法や治療薬を意味する薬の研究に関するものであった。「すべての薬は一般薬か特殊薬のどちらかである。」
一般薬は栄養学でいう6種の非天然物を正しく投与することで成り立っていた。この物質からできたもの(天然物)を使って健康が守れるし、疾病を誘発したり病気を回復させることができる。同じ天然物でも用量によって栄養剤(健康維持)、薬(健康回復)、毒(発病物質)として作用する。入門書には一般薬とともに、特殊な、個性的な、あるいは特異な薬(特殊薬)として分類しているものがある。この薬は動・植物や鉱物性の天然物で、動物薬が人の組織に近く薬よりも栄養物として作用するし、さらに鉱物薬はそれと異なり有毒なため、植物薬が一般的であった。古代薬物学における第一歩は疾病に効く天然物、いわゆる「薬(materia medica)」の調査であった。
第二の課題は植物の薬理作用の強さ(力)で、入門書の著者は作用様式だけでなくその効果にも触れている。「体内における薬の作用は下剤による放出、茹でたイチジクによる保持ないし固定、発熱時の冷水よる効果のように、質の変換には3種の基本的方法があった。また、その作用には下剤による過剰の減少、血液や肉の欠乏時における補給、収斂剤による下痢の止瀉、冷水を適用する発熱の処置など、質の転換に4種の方法もある。」 製剤の作用と効果がまさに薬物学の目標である。
最後は薬とその投与の問題である。薬は内用と外用のいずれでも適用できる。口、鼻、耳、肛門や外陰を通して体内に投与するか、湿布剤、ローション剤、硬膏剤、パップ剤やその類似薬のように体外に外用剤が適用できる。私たちはいま、古代医学の薬に関する理論と実践、すなわち薬、薬物学、薬学の3項目について述べた。つぎに中世の1,000年間について、各時代の進歩を追うこととする。
薬 物 学
薬物学史の世界では一般に長い間、中世の薬草はグレコ・ローマン時代のテオフラストスとディオスコリデスの大著に依存しているにすぎないとされていた。中世の植物学は現在の知識には、あまり参考にならないと思われていた。しかし、ここ数十年にわたる研究で、その考えが非常に変った。中世のアラブ植物学は質・量ともに、地中海の先例よりも優秀だと評価されている。アラブ人たちの規制は厳しくなかった。イスラム教が拡大してアジアとの商取引が活発になったおかげで、薬の貿易が非常に増えた。その結果、植物の鑑定法や
評価法を完成させようとして、薬物学が慎重に研究された。新しい専門書が
誕生した。これを文献的かつ語義論的な手段を使って分析し、アラブの医術がペルシャ、インド、シリア、メソポタミア、ギリシャ、エジプトの遺産を吸収してきたかを立証した。
アル・ビールーニーの著作『薬物療法書』では、薬はシリア、ペリシャ、ギリシャ、アフガニスタン、クルド、インド諸国の方言でも同義語である。薬に関するマイモニデスの論文では、シリア語、サンスクリット語、ペルシャ語、アラブ語、ヘブライ語、ベルベル語、その他の国々の同義語を載せている。確かにこの研究ははじまったばかりだが、アラブの薬物学はギリシャ起源の、とくにディオスコリデスの著作を複製したにすぎないといった、古い考えを払拭することに成功した。M.レーヴェーは代表的な論文である『アル・キンジの薬剤処方集』のなかで有用な薬を統計解析し、収載薬の31%がシリア語、アルメニア語、ヘブライ語、ペルシャ語、そして中継基地のギリシャ語を経由して、古代メソポタミアの学術語に至ることを明らかにしている。このうち23%はギリシャ語起源で、18%がペルシャ語、インド語で13%、アラブ語で5%、エジプト語で3%であった。残りの学術語は追跡調査できなかった。ペルシャ、中国、インドの関係が緊密なことを考えて、ギリシャ語の影響を第3位に落とせば、学術語の各パーセンテージの組み合わせは全体として、メソポタミアの例に近いといえよう。
マーチン・レーヴェーは、この数字を18世紀にアル・サマルカンジが行った『薬剤処方集』の解析で確認している。この研究によればペルシャ・インド由来の学術語は54%、古代メソポタミア起源は20%、ギリシャ17%、イスラム以前のアラブ語が6%、古代エジプトからの用語はわずか2%にすぎない。単一剤や薬の基本の解説に使ったこの文献のジャンルはまことに多彩である。第一に外国語に翻訳するだけでなく同義語のリスト、すなわち原著論文の言葉に相当する薬をアルファベットのリストにする必要がある。アルファベット順にした結果、ビザンチン、アラブ、ラテン文化の単一剤に関する大論文ができあがった。これは、とくにアルファベット順になっていないディオスコリデスの著作に関して、大へん重要な改革であった。実際の内容は直接ディオスコリデスから引用した例も多いが、この構成法を統一したのがガレノスである。まもなく、ビザンチンの医師たちはディオスコリデスの『薬物書』を書き換えた。オリバシウス(325-403年)は薬に関する論文を書くとき、ディオスコリデスの著作を使ったと明言している。7世紀にアエギナのパウロスは、自著の『医学百科事典』の第7巻を薬の研究にさいている。本書は大へんすばらしく、中世の時代に長く信頼された原典である。第1部は単一剤をアルファベット順に配列した研究で、ガレノスにしたがって薬の特徴と適用を各条に整理してある。第2部で複合剤の研究をとりあげて、下剤、軟膏剤、通経剤、解毒剤、丸剤、散剤、シロップ剤、点眼剤、硬膏剤、油剤、芳香剤などに分類している。彼の知識上の指導者はディオスコリデス、ガレノス、オリバシウスらである。ディオスコリデスでなく、ガレノス、アエギナのパウロスの例にしたがって、薬の作用力や効果に順位をつけて評価するという第二の改革が広まった。薬のアルファベット順化と薬の有効度は、中世の薬に関する二つの基本的特徴である。ギリシャとビザンチンの文献が9世紀に、とくにフナイン・イブン・イスハークの学校でアラビア語に翻訳され、その後上記のアジア、メソポタミアの薬物学の伝統と混淆した。ペルシャのアブ・マンスールの著作『薬物の特性に関する書』(970ページ)には、インド薬物学の遺産が相当に入り込んでいるが、この著作で上記のことがはっきりと指摘されている。
一番興味深い著作の一つがコルドバのイブン・サマジャンの『古代および現代の哲学者と医師の単一剤に関する集成』で、薬をアルファベット順に配列している。イブン・アル・バイタールの著作もその例である。アル・ガフィキの『単一剤』もアラブ世界の薬を検討し高い評価をえた論文として、書き留めるべき著書である。その当時よりこの領域は、イブン・アル・バイタール(1197-1248年)の『単一剤』が示したように、科学的になってきた。序文では下記の6項目の研究目標をあげている。a)
ディオスコリデスとガレノスが使った単一剤と過去1,000年に経験した結果を述べること、b) 多数の矛盾点を解決して古代植物学に関する事実を示すこと、c) 反復をさけてはっきりと書くこと、d)
本書をアルファベット順にして使いやすくすること、e) 古今の著作だけでなく、直接体験した薬の適用も詳細に報告すること、f)
別名を外国語で記載し、外国語で薬が入手できるようにすることの諸点である。
中世文学の形式として有名なラテン語の『健康の書』は、1068年にバクダードでイブン・ブトランが著わした原著である。単一剤に必須なデータを表にまとめている。専門的な記述はこの著書から行われたのだろう。『地理に関する書』(アブ・アル・フィダの著作がその例)や『病理学の書』(イブン・ジャズラ)もある。さまざまな書籍の発行によりローマ医学は、このような形で最高峰に達した。
ウィーンで出版したアニスの『健康の書』の本文から例をとる。「外観:温・乾で第3度。選択:大きいもの、南方のもの。用途:胃の冷感と胃腸の鼓腸によく、利尿、便秘の解放と乳汁産生。害:消化の遅延。害の除去:細く砕くかよく噛む。産生するもの:血液。冷と湿の気質、高齢者と虚弱者、冬季と北部、本剤がみつかった地域に適合」。
本文でみられるようにスコラ哲学の形式は最高の高さに達していた。
10世紀からずっと植物学と薬物学の文献は、サレルノ、シシリーなどを経て西ヨーロッパに伝わった。このようにラテン医学は単一剤と複合剤を含め、数100種であったギリシャの百科事典に比べて、4,000種以上の薬というまことにすばらしい数字になった。鉱物、植物、動物のデータが単一剤や基本薬の論文とともに、たくさんの宝石細工術、植物標本、動物寓話集の完成に役立った。このうち出色なのはラテン・ヨーロッパでできた『マーケル・フロリデス』という説教詩で、9世紀末近くに書かれ相当に普及した。ここではペドロ・カベッロ・ド・ラ・トーレの翻訳書のなかから、ヒメウイキョウの種子に関する本文の数行を一例として紹介する。「ヒメウイキョウの力は熱と乾で第3度である。とりのぞくものがあれば内蔵から空気を排出する。本剤は胃の重さと闘い、胃と肝臓の消化熱を刺激する。性病の炎症を消失させる。食酢と茹てれば腹の下痢を固める。ワインと一緒にとれば有毒な咬傷だけでなく坐位呼吸を治療する。専門家がヒメウイキョウをオキシクラと併用すれば、睾丸炎が寛解すると述べている。また、豆の花粉と熱い蜂蜜を粉砕・混合した後に適用すれば、同じような効果がえられる。ヒメウイキョウをオキシクレートと一緒に服用するか塗布すれば、正常な月経になる。頻回に噛めば皮膚の外観は蒼白になる」。
理 論 薬 物 学
薬物学は薬の科学である。治療に関する経験的あるいは実践的な知識の問題ではなく、薬を科学的に理解することである。経験主義者は投薬で痛みが軽減したり、熱が下がるのを知るだけで満足するだろう。しかし、薬物学者はその過程の本質、つまりどんな薬が痛みを軽減するか、その理由と方法を理解しなければならない。アリストテレス以後、古代の医師たちは、真の薬物学者が治療の質(what)と治療作用の機序(why)がわかっていると確信していた。その後、薬剤師は偶然に遭遇した経験だけでなく、薬の科学も身につけて治療の本質と個々の理由を理解するようになった。古代の薬物学者は私たちとまったく違った方法で、同じ目標である薬の特異性について知識をえようとした。
薬物学がいかにして学問になったか。また、なぜ薬なのかその理由を確めるステップはなんだろうか。ガレノス医学の時代では答えがすべて同じで、第一は薬の原料(試料)の外観分析(質の分析)、第二が単一剤の力(有効性)を知り、第三が活性や作用過程の機序を研究することであった。外観、力、作用が薬の科学的研究の重要な3要素である。たとえば、アヴィセンナは薬物学の研究を中心とした『医学典範』の第2巻の第1章で外観、第2・3章で薬の力や効力を、第4・5章は作用をとりあげている。これら三つのテーマを簡単に調べてみよう。
エンペドクレスの教えでは、例外をのぞけば古代の医師は自然のなかで、4元素(空気、水、火、土)が身体を構成すると考えていた。1種以上の元素がそれぞれの比率でさまざまな質や特性を生みだす。土が優位な身体は、たとえばほかの基本元素の空気がもつ熱・湿の外観よりも、乾・冷の質・体質・気質になる。したがって、自然の万物はこの原理で構成され、その外観を決定する優位な一組の質をもっている。人生のはじめはいつも湿が優勢であり、終わりには身体が冷を主とした状態になりやすいので、この体質は一生を通して同じ状態ではない。
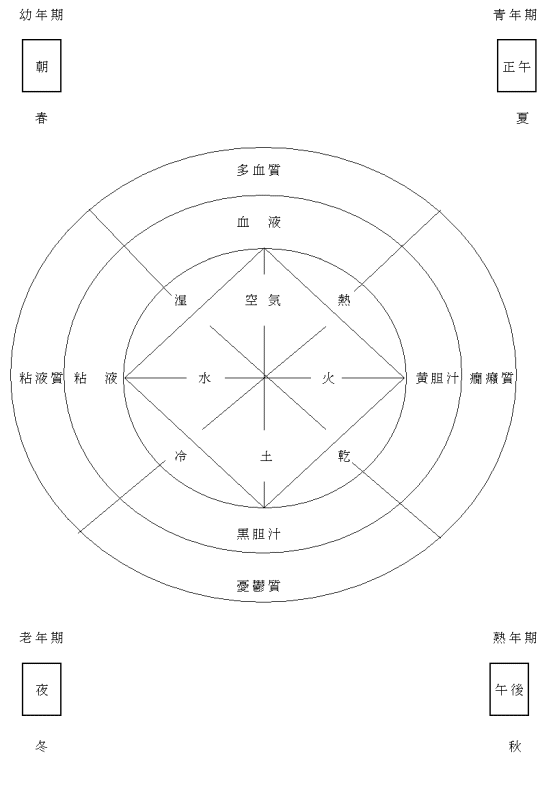 |
冷の植物は夜・冬の老人に投与すれば非常に効果的で、また正午・夏の青年ではその効果が弱まる。「薬の効果」はその外観に関連するが、完全に一致するわけではない。正確な関連性は中世薬物学で一番の論争点であった。ガレノスは薬の効果や効力を4段階の評価とし、さらに0度(緩和)を追加した。この評価によれば「0度(緩和な)」薬の使用とは、投与した身体のどこにも効果が現われない場合である。熱で第1度の薬とは意識しないと感知できない微細な作用を起こすものを指す。第2度の薬は効果の発現があるもの。第3度は大きな効果があるもの。第4度の薬は強すぎて患者に障害を起こす点数である。この評価を活用するのが難しいので、投与薬の活性度を決める場合は薬物学者が行う。8世紀にこの方法をさらにすすめ、薬の有効度と優位な質(外観)の強さとの関係が確立した。土1、火2、空気3、水4の割合の基本4元素からなる植物の有効度を問題としてとりあげる。各元素は2種の質、たとえば水は冷と湿をもつ。この植物の外観はすでに述べた通り優位な質により決定する。この例では優位な質は冷と湿で、ともに水の元素に依存している。このため、その力は4になり反対にほかの元素の質はそれぞれ3、2、1である。しかし、もっと慎重に解析すればこれらの級(度)は単純化しすぎていて、すぐに事実を曲げていることがわかる。第一にこの植物では湿と冷は同等でない。湿は水の元素4と空気の元素3を共有する質だからである。したがって、湿の程度は実際に7で冷の程度は5になる。ほかの質も同じ方法で考えれば熱が5で乾が3になる。その結果、割合は湿が7、冷が5、熱が5、乾が3となる。このため優位な質は湿となる。しかし、質は単独でなく反対の質と一組になっているので、優位な2種の質は湿7と乾3になる。すべての外観は活性だが、もう一組の熱5と冷5は優位でない。ここで例示する数字がもっと小さければ、熱と冷は熱6で冷2のように異るただろう。これまでは湿-乾が優位な組み合わせだったが、この場合は湿・熱の2種が最強の質である。この2種の質しか発現できない(ほかの質は無効)。こうした理由で2種の質だけが認められる。このように薬物学者は単一剤の最強の質と外観が決定できる。
さて、ここでは複合剤について考察し、そのなかに含有される単一剤のあり方を検討する。このテーマはあまり簡単ではないが、1975年にミッチェル・R・マクボーが『中世薬学理論の発展』と題する研究論文を出版してから、よく理解されるようになった。古代の医師たちはアリストテレスに典拠し、各単一剤の力(潜在力や効力)が複合した形で存在すると考えていた。しかし、これは二つの異なった理論で解釈され、ともに中世薬物学の擁護者となった。中世の著作では、複合剤の特性が単一剤の特性を混合したものだと考えていた。マクボーは「混合する特別な理由は著者によって多少異なるが、ほとんどは複合剤の各成分が個々の特性を保持したままであるという暗黙の前提が基本」と書いている。その一方で、アヴィセンナは、単一剤が「発酵」という複雑な相互作用の過程を経て、複合剤となるという意見であった。「発酵」によって独自な外観や本質的な外観を呈し、複合剤を構成する単一剤とはまったく違った質になると考えた。マクボーは「実際に独自な外観は、異なった度数の質をもつ薬の外観と関係がない」と述べ、したがって、「私たちは体系的に単一剤から複合剤の多数の特性を予測できるが、薬の独自な外観、つまり薬に固有な質は使用経験によってのみ決まる」と述べてている。しかし、ガレノスの伝統では複合剤の薬物学的性質は、単一剤の質から推定できることが多い。アヴィセンナの考えとは違っている。マクボーは「13世紀以来、薬物学で不明な元素に記号を使ったのはアヴィセンナであり、ガレノスが元素の不変性を象徴化したことは確かだった」と締めくくっている。ガレノスの意見に焦点を合せれば、複合剤の質が単一剤の質に由来することがわかる。アヴェロエスの一例にならって、2種の単一剤(熱で第4度の強さと、冷で第2度の強さ)からなる複合剤をとりあげる。反対の質が一方の質を減らすので、この複合剤は熱で第2度になる。マクボーが定めた記号の注解を使えば、つぎのように書くことができる。
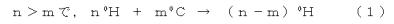
しかし、複合剤が同じ優位度の質をもった2種類の単一剤からなることもある。上記の式を使えば、この複合剤の質の強さは単一剤の強さの合計となる。しかし、きわめて論理的な理由で、本法ではうまく解けない。結果は主たる質の強さの平均である。セラピオンの原典に「私たちは熱の外観で緩和(0度)より上の第3度の薬と、熱で第5度の外観の2種の薬をみることが多い」とかなりはっきりと書いている。両者を混合すると外観は2者の平均値になるだろう。したがって、熱で緩和(0度)を超えた4度の外観になる。「
これは記号でつぎのように表わすことができる。」
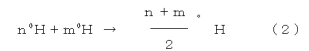
単一剤と複合剤の外観が解決すると、薬の治療効果に関する問題解決に好都合である。前述した薬の外観に関する理論と、薬の力の4種の水準(薬の有効度)について、上記のガレノスの学説との関係を確立すべきである。最初に式を定義したのは、アラブの医師アル・キンジ(837年頃)であった。アル・キンジによれば、薬の有効度が高くなるには、優位な外観の質が等比的に上昇する必要がある。比率を表1に示した。
一組の反対の質(熱Hと冷C)の外観と薬の有効度の関係は下記の式となる。

解決すべき問題が一つ残っている。強さに関する薬の混合量、すなわち量と質を調整する方法で、これは複合剤に使う単一剤の量を決めるのに必要である。アル・キンジは、マスティック(熱で第2度)とカルダモン(熱で第1度)の2種の単一剤を含有する成分の複合剤をとりあげて、下記のように解答している。
表1.
マスティックを2ドラム、カルダモンを5ドラム秤った。アル・キンジ法によれば、各単一剤の優位な質は、その薬の熱の度と用量の積である。したがって、マスティックの優位となる質は4で、カルダモンは5になる。低位の質は前述の比率(表1)によって計算する。マスティックが熱で第2度なら熱は4で、冷は表から1/4以下の1である。カルダモンでは熱の第1度で2となるので、結果は冷がその1/2で2.5になる(表2)。
表2.
関係式 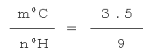 である。 である。
比率表1で量が1/4(反対の質が第2度)以上で、1/2(第1度)以下である。
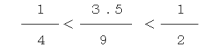
結果として、熱の質は第1度と第2度の間にある。
アヴェロエス(1198年に死去)も『大集』の第5巻第1章でこの問題を分析し、やがてアル・キンジ法とはかなり違った方法で(アル・キンジ法は少なくとも、彼の弟子の医学者が説明)解答をだしている。外観の質と薬の有効度の比率は表3になる。
アヴェロエス法では外観の質と有効度の関係が次式で説明される。
表3.

優位な外観の質は下記の等差数列に置換された。マクボーによればこの学説をアヴェロエスのものするのは不合理のようだ。しかし、中世初期のラテン世界では、彼の名で伝わっていたことは確かだろう。アル・キンジ法の例で述べたように、アヴェロエス法には複合剤の最終の度(級)や強さに対する単一剤の混合量の影響という未解決の課題もある。すでに単一剤の優位な質の強さが複合剤の総合的な外観に影響することを明らかにしてきた(式1)。
この式に二つの変数(重量と混合比)を導入することが重要である。熱でn度の単一剤の量をxとし、冷でm度の単一剤の量をyとすれば、その解は次式である。
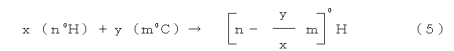
本法で複合剤の量・質の関係を計算するが、前出の混合時に対応する反対の質を考えずに優位な質だけを考慮したアル・キンジ法とは異なっている。その場合、量での掛け算の値は優位性しか影響しない。アル・キンジ法とアヴェロエス法の違い(等比的と等差的)を考慮せずに外観と有効度の双方に等差数列を使うと、複合剤の質-量関係を違った方法で処理し比較することになる。具体的な例で立証する。熱で第3度のコショウと、冷で第1度のスミレの2種をとりあげる。前者1ドラムと後者15ドラムの混合を想定する。熱と冷の強さはアヴェロエス式とアル・キンジ式では異なる。4表に示す。
この場合アヴェロエス法では複合剤は多くは第3度になる。
一方、アル・キンジ法によれば、複合剤の有効度は0度(緩和)と第1度の中間になる。
アヴェロエス法の例で、式5を使えば
表4
薬物学の伝統はサレルノのアフリカ人コンスタンチンの『処方書』(1087年)や、ウルソの『処方』(1170-1200年)を経由してラテンの世界に入り、モンペリエでヴィラノヴァのアルノウが1300年頃に『処方名鑑』を書いて最高の水準になった。アルノウはアル・キンジ法で提起された複合剤の外観と有効度の決定問題を解明する。与えられた複合剤中の単一剤の有効度をa、b、c.....と分類し、外観iを次式で示した。
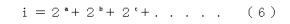
したがって、たとえば一つが冷(C)で第1度、もう一種が熱(H)で第3度の 2種の単一剤からなる複合剤は次のようになる。
iC=21+20=3
iH=20+23=9
複合剤の外観がわかると商 iC/iHは比率表で比べたように分数1,1/2,1/4,1/8,1/16となり、薬の力や有効度を正確な数か概数を示す。
単一剤と外観にもとづいた複合剤の計算で、量に関する問題は外観と薬の有効度の関係のように、アルノウがアル・キンジ法に沿って解いている。しかし、アルノウは前記の式5にかなり近い手法を使うアヴェロエス法から、単一剤の質が複合剤の質に最終的に影響する方法にとりかかった。この方法で二つのアラブの伝統のアル・キンジ派とアヴェロエス派がアルノウの業績で統合された。この点からすれば、モンペリエで『処方』は大へん適切なテーマをえたことになる。ベルナール・ド・ゴードン(1303年、『処方要綱』)、ジョーダン・ド・トゥーレ(1326年、『処方発見』)、ジェラード・ド・ソロ(『イヴェナム入門』)は、この主題をとりあげている。一般にこうした言葉は医師にあまり認められないまま、モンペリエからスペイン、フランスに広がった。14世紀の哲学者はその点に大へん関心をもった。オックスフォードのマートン校で『処方』が熱心に討論された。サイモン・ブレドンとウォルター・オディングトンはそのことを書ている。また、トーマス・ブラッドワーディンも『比例方鑑』(1328年)で、身体の速度を決める運動の強さと抵抗の関係を説明する法則を定めているようだ。アル・キンジの著作で述べているように、この法則で運動の強さと抵抗の関係が等比的に増加する場合、身体の速度は等差的に増加する。しかし、催吐、緩下、収斂など特異作用という重要な未解決の問題は、薬の効果と効力に関する枠組みの下に存在する。この特異作用は経験を通して知りえたが、どんなに複雑に理論化しても十分に説明できない。
ギリシャでは理性と自然(思考と経験)が分離し評判がよくなかった。このおかげで薬物学者は薬の主作用・普通の作用(熱、冷、湿、乾)と二次作用・特異作用(催吐、緩下、鎮痛剤など)に分類してしまった。薬物学者は主作用を経験よりも理性で理解している。一方で、二次作用の知識は真の思考(理性)でなく経験から学びとっている。古代の薬物学が抱える隠れた矛盾や不調和は、ここから発生している。結局、私たちが検討した計算では薬の「特異作用」が決定できず、この因子は概念のうえで理解されなかった。古代の薬物学は「特異作用」について、適切な理論を創ることができなかった。これは17世紀のキニーネ論争でもっと鮮明になる。キニーネの解熱作用は明白で、経験で裏づけられ疑いの余地がなかった。キニーネの主たる質は熱であり、発熱の処置に使えば逆の治療になってしまう。近代薬理学は医師が古い第二の質や薬の特異的な力を重視することからはじまった。
理論薬物学の第3章では二つの言葉があり、「外観」につづく処置が第一で、「効力」(力、薬理作用)を使った実践がその二である。薬は下剤による排出、収斂剤の保持、水による発熱の抑制のように、種々の処置や実践で質を変える。こうした処置は薬の効果と患者の体質の影響を受ける。薬物療法の最終目標である患部への適度な効果は、不足する質の代替物を補充して、過剰な質とその反対の質の均衡をとる場合のみ達成できる。冷で湿の薬は熱で乾の外観にだけ推奨される。質や物質の消耗が大きい場合は収斂剤がすすめられる。互いに逆の元素で治療することが、古代薬物学における黄金の法則である。
中 世 の 薬 学
中世の「薬学」という言葉は、単一剤を配合して複合剤や解毒剤を創る科学技術を指している。医学百科事典の巻末によく解毒剤が登場するが、このような薬物学と医学の連携もこれが最後である。アヴィセンナの『医学典範』第5巻の巻末は、複合剤と解毒剤の研究にあてている。解毒剤の製法が徐々に医師から専門的な薬剤師の手に移ってきたからである。薬剤師の親方は非常に経験に富む職人である。彼は小売業者で医師よりも下の社会的、文化的階層になった。独立した職業としての薬局は、9世紀の前半にアラブ世界でよく記録されいるようだ(ハメネフ)。
そこから9世紀(以前であろう)に西洋のラテン世界に伝わった。この時代には他の地方と同じように、イタリアとフランスの南部に公営薬局があったことがわかっている。複合剤を正確に造りあげるには、配合成分の量・質を決める理論的な根拠だけでなく実用的な知識も必要である。良質な複合剤を配合するには、ワインの製造に劣らず複雑な工程を慎重に取り扱わなければならない。ワイン製造のように時間と技術が欠かせない。アヴィセンナは『医学典範』で単一剤が「発酵」と称して長期間、相互作用を受けざるをえないと書いている。セント・アマンドのジョンは、この期間が数ヶ月間におよぶ可能性があり、単一剤は長期間の工程の最後になってはじめて変質し、新しい複合剤ができると考えている。新しい薬の外観と有効度は、もとの単一剤の性質からはまったく推測できず、またその理由は純理論的でなく経験的なものである。セント・アマンドのジョンは薬が「熟成」するといっている。アヴセンナの発酵のように、この「熟成」は単に物理的な変化だけでなく化学的にも変質する。実際、錬金術的にも良好な状態である。
錬金術の目的がまさにこの通りで、変質工程を制御して新しい天然物を人為的に製造することであった。古い職人が偶然の変質にめぐり遭った場合、彼は単なる自然への協力者にすぎない(たとえば、大工は木を作らず、細部・形を変えるだけ)と考えれば、錬金術師と薬剤師に近い人は、それ以上のことをしていることになる。本質的な変化、物質の変換を起こし、新しい天然物を創ろうとした。これが錬金術師の革新性と頭痛の種である。錬金術師は自然の創造について神と競った。この悩みの種である矛盾が解決したのは、近代社会になってからであった。
薬の組成と製剤に関する基準作成の必要性が一つの図書様式を生み、これが中世の時代に広まった。この処方集はアラビア語でアグラバドヒン(agrabadhin)、ラテン語でアンチドータリア(antidotaria)である。アル・キンジの著書は、メスエ青年、イブン・カイサン、アル・サマルカンジの著作などとともに、第1分野(アラビア語)のなかの傑作であろう。ラテン語の著作ではサレルノで組まれたニコラス・プラポシトスの『ニコライの処方集』がとくに有名である。マックス・ノイベルガーが『基礎最新薬局方』で述べているように、ニコラスは彼以後に登場した薬局方の基準となった。この教本の注解書は有名で、とくにマットテウス・プラテリウスが一番知名度が高いようだ。この図書様式の情報はガレノスの『治療術』に記載されている。すべての文献の目次はいつも同じで、薬の性状、製剤の形、製品を収載していた。よく収載される剤形はシロップ剤、舐剤、水剤、油剤、丸剤、糖加剤、ローション剤、エセンス剤、ジューレプ剤、煎剤、潅流液剤、温湿布剤、散剤、歯科用剤、うがい薬があり、点眼剤、浣腸剤、坐剤、ペッサリー剤、吐剤、利尿剤、通経剤、解毒剤、催淫剤、発汗剤なども採用されている。基本的にこの武器庫は今日までつづいている。
|
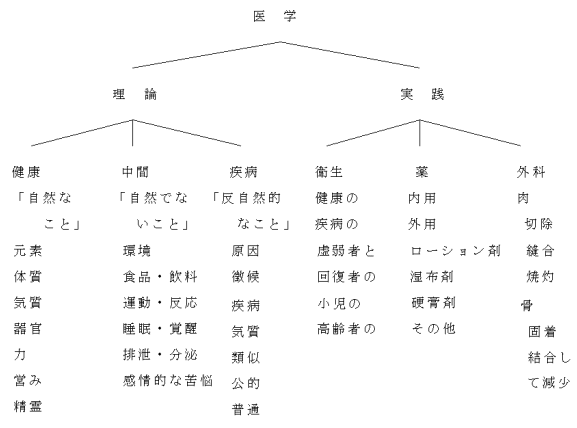
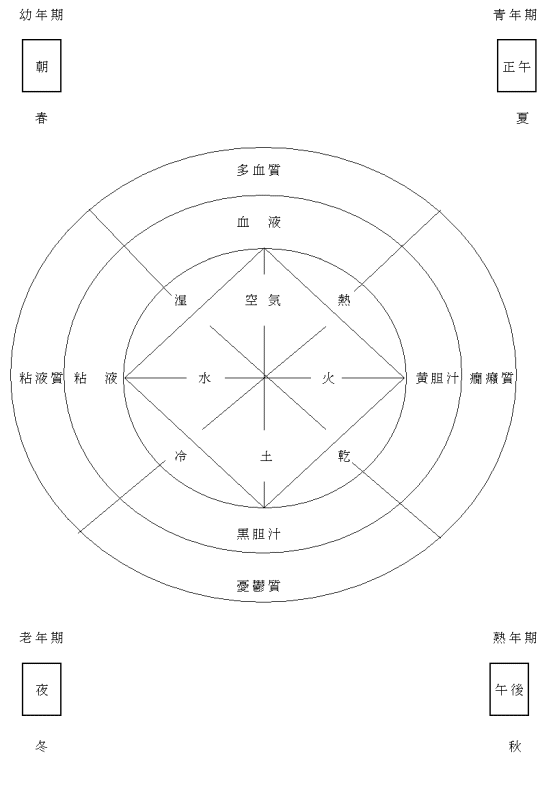
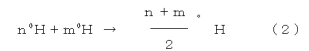
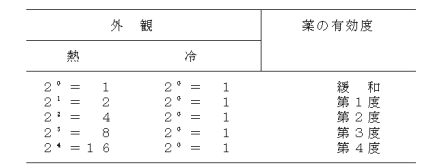
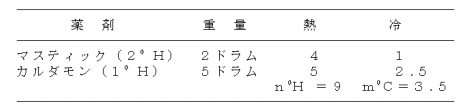
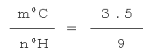 である。
である。