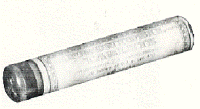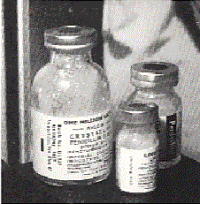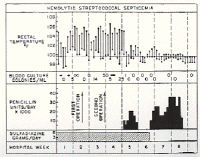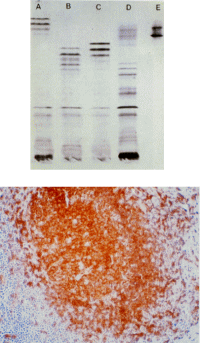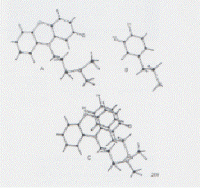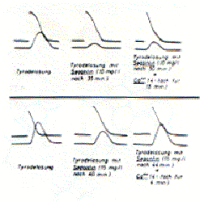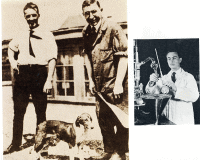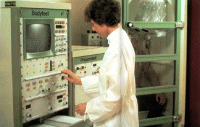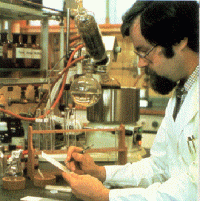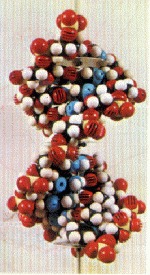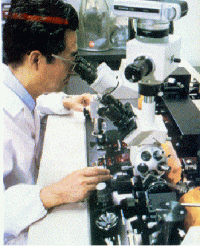|
一般に近代の薬物療法は、1910年にエールリッヒのサルバルサンではじまったとされている。抗菌剤による化学療法の領域では他の治療分野と同ように、1935年にスルホンアミド剤が導入されてから本格的に発展した。スルホンアミド剤は化学療法に関して画期的な出来事であった。この薬のおかげで発想が刺激され、創薬が活発となり、多方面にわたって薬理学の価値が高まった。
最初のスルホンアミド剤スルファクリソイジンは、エールリッヒの教示により合成された。彼が頭に描いたのは有毒な核(−N=N−基)と細菌に親和性を有する薬であった。ドマークが行った実験的な感染症は治療が成功するとともに、すぐに反対の知見が現われたが、この理論は支持されたようだ。
フォーニューとそのグループは、スルファクリソイジンの活性が−N=N−基結合が開裂して生ずるスルファニルアミドにあることを立証した。化学的本体は1908年以後に解明された。一方、1940年頃にスルホンアミド剤がとくに細菌を狙う「毒矢」ではなく、細菌の発育に必須な代謝物の競合相手だったという証拠がえられた。スルホンアミド剤は細菌の代謝反応に必須な化学物質に類似し、代謝を阻害して細菌の発育を抑制する作用もつ薬であった。この発見で化学療法におけるエールリッヒ説の価値が低下したが、癌の化学療法から高血圧症の治療まで、薬理学の多数の分野における将来性が証明された。抗菌化学療法の領域ではパラアミノサリチル酸(1946年)、抗結核剤のチオセミカルバルゾン剤とイソニアジド(1952年)、ピリメタミン(1951年)のような抗マラリア剤(1951年)、抗菌剤で抗マラリア剤のトリメトプリムの発見に結びついた。スルファクリソイジンの活性成分スルファニルアミドの同定が、毒性の低い強力な誘導体を合成する機会を与えた。数年間で6,000種のスルホンアミド剤を合成して実験したが、治療に役立ったのはわずか数種類であった。1942年にスルホンアミド剤が最初に導入されてからまもなく、構造・活性の相関を研究していた二人のアメリカ人の科学者が、まったくの好奇心から最強の誘導体はすでに合成され、もうこれ以上強力な薬は合成できないと予想した。40年後、この予想は的をえたようだ。
スルホンアミド剤の誘導体が激増して使用が普及するにつれ、副作用の情報が大量に増えてきた。副作用のため多数の誘導体が消え去った。しかし、その一方で、副作用は新しい薬理作用をもつ薬の開発にとって、非常に重要な糸口となった。スルファニルアミドを投与した患者で代謝性アシドーシスが観察され、これが腎臓の生理で重要な役割を果す炭酸脱水酵素を阻害するために起こることがわかり、利尿剤アセタゾラミドの合成と開発を生んだ。その後、昨今を問わず、水分の貯留と高血圧症を治療するすばらしい薬であるベンゾサイアザイド剤の開発がづづいた。実際、フロセミドとブメタニドのように、新しい最強の利尿剤はスルファニルアミドの直系の子孫であると考えられるし、抗痙れん剤と経口血糖降下剤の分野も、同じ親化合物と線で結ぶことができる。
抗 生 物 質 療 法
抗生物質療法の発明者フレミングのイメージは、すっかり定着しているので、価値のある貢献に対して、控え目に評価するのは非常に難しい。2,500年前の中国で青カビが生えた大豆の凝乳を、皮膚の感染症の治療に使うよう進めている。ペニシリウム属がきわめて普通の青カビであることを忘れてはならない。それほど遠くないが、フレミングよりずっと前に光の回折に関する研究で有名なチンダルが、細菌が発育して濁った溶液の表面にペニシリウム属を生長させると透明になると述べている。1939年にデュボスが抗生物質グラミシジンを発見しているが、1928年にフレミングがペトリ皿に混入したペニシリウム属の周辺で、接種したブドウ球菌が溶解する現象を観察している。これを高く評価するのが適切のようだ。フレミングはこのカビが産生し細菌を溶解する物質をペニシリンと名づけるとともに、この物質が治療に適用できる可能性にも触れている。アンドレー・メロー著の「公的な」ペニシリン史で、フレミンングの上司アーモス・ライトにペニシリンについてすぐに行動しなかった責任があると書いているが、今日では大へんに疑問である。
ペニシリウム培地からペニシリンを分離したのはフォーリーとチェインで、1940年に化学療法剤の一種だと同定している。工業生産は第二次世界大戦中に行い、近代抗生物質療法の大黒柱の一つになった。
忘れがちだが、ほかにも重要なステップがある。1939年から1943年にワックスマンのチームが、抗生物質を同定して分離するスクリーニング法を開発している。このシステムは今日でも有用である。ワックスマンはストレプトマイシン(1944年)の発見でも有名である。この抗生物質は大英医学研究協会の臨床治験のテーマである抗結核作用を有する物質で、薬の臨床評価で貴重な新発見として広く認められた。
ペニシリンとストレプトマイシンの後にも、抗生物質の発見がつづいた。チフスに有効と証明された最初の薬クロラムフェニコールが、1947年にはじめて人に投与された。最初のテトラサイクリン剤が1948年に登場した。その後、ほかのテトラサイクリン剤もつづき、1952年に最初のマクロライド剤のエリスロマイシンが開発された。
多種多様な資源から強力な抗生物質が分離されて、とどまることがなかった。しかし、この領域でもう一つの発展が注目の的であった。細菌のアミダーゼを使って大量のペニシリン誘導体が工場で生産できるようになった。6-アミノペニシラン酸の大量生産が可能となった。細菌のペニシリナーゼ分解作用や胃液に抵抗性をもつものや、広域の抗菌スペクトルを有するものが現在使用されている。一方、ペニシリン関連物質のセファロスポリンCに同じ製法が応用されて、セファロスポリウム属を起源とするセファロスポリン剤が、菌の増殖速度とあまり違わない速度で増えているようだ。さらに、βラクタム構造は長い間、ペニシリン剤やセファロスポリン剤以外に可能性は少ないとされていたが、さまざまに修飾できることがわかり、新しいβラクタム系抗生物質のめざましい成長が期待されている。
悪 性 新 生 物 に 対 す る 化 学 療 法
ここでは再び第二次世界大戦にもどって、この領域の創世期を調べてみよう。抗悪性腫瘍剤の化学療法で最初に登場した薬は、化学戦争に関連して秘密裏に研究し開発された。第一次世界大戦で使ったマスタード・ガスのリンパ球溶解作用が、これと密接に関連するナイトロゲン・マスタードの合成と癌への適用を生み、大へん興味深い結果になった。最初のナイトロゲン・マスタード(メクロレタミン)が1942年に癌に試用され、その成功が多数の誘導体を生み、なかでもクロラムブチル(1953年)、メルファラン(1955年)、シクロホスファミド(1958年)はとくに注目に値する薬である。
抗微生物療法のように、抗代謝剤の合成は非常に強力で有用な抗新生物剤を生んだ。葉酸の同族体メトトレキサートは、短期間だが白血病を著明に寛解させ、1952年に報告されたヒポキサンチン同族体 6-メルカプトプリン、ピリミジン誘導体で1957年に登場したフルオロウラシル、そして1961年のシタラビンはいずれも主要な抗新生物剤である。抗微生物剤と抗新生物剤の分野では、有用な薬が自然を起源とする点が似ている。抗新生物剤のなかでも細胞毒性を有するビンカ・ロサエ(ツルニチニチソウ属)のアルカロイド、ストレプトミケス属が産生する抗生物質ダクチノマイシン、ダウノルビシン、ドキソルビシン、ブレオマイシン、ミトラマイシンが現在使われている。
1964年に抗新生物剤療法で最初に試用した酵素アスパラギナーゼは、とくに論評しなければならない。正常組織はアスパラギンを合成できるが、新生物細胞は外部からアスパラギンの補給が必要との理論にもとづいて使用された。外部からアスパラギンを補給せずに癌細胞を死滅させる方法とは、最初に正常細胞と癌細胞間の代謝の相違を確認して、これを治療に応用することであった。残念なことに、最初の見込は具体化しなかった。アスパラギナーゼは短期間しか有効でなく、重篤な副作用がたびたび随伴した。
はじめてナイトロゲン・マスタードで治験してから40年以上たっているが、抗新生物剤の化学療法はまだ、細胞毒性剤を使用しているし、薬はきわめて強力で有用性は限られている。真の治療はある種の新生物に限られており、この種の化学療法に多くのものを期待するのは無理のようだ。むしろ自由な方向にむかって努力するのを眺めるか、薬の開発を完全な円運動だと考えるのも当然だろう。毒矢を使ったエールリッヒの独創的な概念は、今日では実現している。モノクローナル抗体は、リチンのような有毒分子を特異担体として使用する可能性を示す。
抗悪性腫瘍療法への取り組みとして、腫瘍の血管形成を抑制する方法もある。たとえば、増殖中の新生物への血液供給を遮断する方法である。軟骨組織に存在する血管形成阻害物質は、この組織の新生物の侵入に対する抵抗性とともに長い間知られていた。しかし、この因子の性質が姿を現わし、抗新生物療法としての可能性が明らかにされたのは最近のことである。癌との闘いで細胞毒性剤による治療法から抜けだそうと、新しい取り組みが行われている。
精 神 薬 理 学
最近でも、想像しなかった新しい薬理作用を有する薬が多数開発されているが、精神薬理学の誕生も50年代における薬学革命の画期的な事件である。世紀の変わり目にはせいぜい3〜4種の鎮静剤しか使えなかった。有効性は低く毒性もかなりのものであった。
1903年にバルビツール酸塩が登場した。有効性とある程度は耐えられ点で、確かに進歩したが、精神薬理学の真の開花は、1950年頃に数世紀の間インドで使っていた薬用植物ラウフォルフィアの抗精神作用が西洋で認められ、クロルプロマジンが発見されるのを待たねばならなかった。クロルプロマジンは全身麻酔剤の研究中に、強い精神症状を抑制する薬として合成された。しかし、本剤を精神病の治療にはじめて使った臨床研究者たちは、賢明なことにクロルプロマジンが不安と興奮の症状を解放する以外にも、多数の薬理作用を示すことに気づいた。化学構造や薬理的な面で密接に関連する薬もつづき、ハロペリドール(1958年)で新しい化学の展望が開かれた。
精神分裂病に無効だが、正常状態では軽い鎮静作用を現わす意外な性質があり、有効な抗うつ作用をもつ化合物イミプラミン(1958年)が、クロルプロマジンの構造を修飾することで誕生した。まもなくこの領域にも新薬が参入した。親化合物の構造に近い薬もあり、まったく異なるものもあった。しかし、クロルプロマジンと同ように今日なお、イミプラミンは精神薬理学でもっとも価値ある薬の地位を占めている。
1960年頃にクロルジアゼポキシドが登場している。いまでも跳躍台の出発点として認められるだろう。これは最初のベンゾジアゼピン系の薬で、薬理学的な関心はあまり高くなかったようだ。この新しい鎮静剤は耐容性が良好で使いやすいが、特徴がはっきりしなかった。市場を広げるために徹底した研究が行われ、やがてベンゾジアゼピン剤は一般的な抗うつ剤でなく、確実な抗不安作用を有する可能性がでてきた。中枢神経系におけるベンゾジアゼピン受容体の発見と、特異的拮抗剤の合成はさらに大きな発見であった。ついにベンゾジアゼピン拮抗剤を静脈内に注射して、速やかに健常者を不安に陥れることに成功した。これは精神科療法の生物学基準に興味をもつ人にとって、わくわくする発見であった。さらに、ある種のベンゾジアゼピン剤は重要なてんかん治療剤となり、強力な鎮痛作用をもつ誘導体もごく最近になって合成されている。
心 血 管 系 の 薬 理 学
心血管系疾患の治療薬は、ジギタリスのように寿命の長い薬もあるが、ここでは再び40年代に逆もどりして、今日のめざましい成功の出発点をみることにしよう。大へん面白いことに、最初に注目するのは薬でなく専門分野である。1920代後半のゴールド医師は薬理学と臨床医学に興味をもっていたが、人におけるジギタリスの効果について研究を開始した。人での薬理学に定量法を導入したゴールドの業績は、英国でその後に開発された臨床治験法とともに、臨床薬理学の基礎をきずいた。臨床薬理学はゴールド自身が創った専門分野の用語である。
1920年代に行ったアドレナリン作動性伝達物質の分子修飾で、アドレナリン作動性β受容体を特異的に刺激する非常に有効な最初の抗喘息剤イソプレナリンや、血管収縮性で鼻充血除去剤として繁用されるフェニレフリンが開発された。興味深いことに、1962年にこの分野で最初に開発したクロニジンは、志願者に投与すると徐脈と降圧が生じた。その後本剤の作用は立証されて、アドレナリ作動剤の研究とって優れた道具になるとともに 降圧薬の仲間に加わった。アドレナリン受容体の研究分野では、ジクロイソプロテレノール(1958年)の登場が自律神経の薬理学に役立った。本剤は有用な治療薬でなかったが、β遮断剤の発見に結びついた。この領域での最初の薬プロプラノロール(1964年)は、やがて不整脈、狭心症、高血圧症、片頭痛に有効なことが立証された。プロプラノロールおよびβ遮断剤の使用についての可能性は、近代薬理学の進歩に動じない人でもびっくりするほどである。
心臓の冠状動脈疾患に適度な効果をもつプレニラミン(1960年)は、細胞内のカルシウム・チャンネルを遮断する薬で、新しい薬理作用の発展に重要な役割を果した。ヨーロッパの研究者フレッケンスタインは、1967年にプレニラミンの潜在作用を変えずに、心筋の収縮力を低下させることができ、その作用はカルシウムで阻害されると発表した。数年後「カルシウム拮抗」の概念が確立し、心臓の冠状動脈疾患、不整脈、高血圧症、片頭痛などを治療する新薬が医療のなかに華々しく参入した。
生 物 学 的 製 剤
1921年にホルモンの薬理学で重要な動きがあったとする意見に反対する人はいないだろう。当時、バンチングとベストがインスリンを分離し、1922年にはじめてそのホルモンで14才の糖尿病患者を治療することができた。その後もホルモンの研究はつづいている。今世紀の中葉にコルチゾンが分離され、抗炎症作用が発見された。まもなくプレドニゾロンが登場し、それからは想像できないほどの有効性をもった多数の「副腎皮質ステロイド」が開発された。
ほかの領域ではロック、ピンガス、ガルシアが黄体ホルモン剤を使って婦人の不妊症を治療しようとしたが、製剤中に混在した卵胞ホルモンが予想外の原因となって、経口避妊剤の開発をもたらした。これは医療や心理および社会的な諸相で大きな影響を与えた。
この時代は進歩のパターンがすべて同じであった。たとえば、ヘパリンやウロキナーゼなどのホルモンや生物学的製剤が同定された。これらの分離や合成も達成し、努力のほとんどが製剤処方(長時間型インスリンがその例)や異なった特徴をもつ同族体の合成(とくに鉱質副腎皮質ステロイド活性をもたない副腎皮質ステロイド)に傾注された。
遺伝子工学の発展でこのパターンが完全に変わり、まさに進歩の速度が早まるだろう。天然資源から獲得するのが非常に難しい薬やまったく入手できない物質を、急速に増殖する細菌を使って大量生産しているか、あるいは近い将来製造することになるだろう。純粋なインターフェロン、ヒト成長ホルモン、ソマトスタチン、ヒトインスリン、血栓の治療にきわめて有効な組織プラスミノーゲン活性化因子による治療が現実のものになりつつある。
薬 物 療 法 の 将 来
1940年から1960年の間に多数の新しい製剤が登場し、「薬の洪水」という言葉が当たり前になった。なかには不運な発展により新薬の参入速度が数年間遅れたこともあったが、多くの関係者は第二の薬学革命の時代にさしかかったと考えている。生物工学はまもなく癌やほかの分野で強い影響力を発揮するだろう。産業微生物学は感染症や新生物の領域を大きく越えながら、薬の開発にとって巨大な資源になりつつある。微生物の副産物(代謝物)を薬学的に使用する点では、抗生物質は氷山の一角を示すにすぎないだろう。トリポクラジウム・インフラタムが産生するシクロスポリンは、臓器移植後の拒絶反応しか有用性がない珍しい新免疫抑制剤である。ストレプトミケス・アヴェルミチディスの培地からえたアベルメクチン類は、低毒性で有効な駆虫剤であり、また殺虫剤でもある。ペニシリウム・シトリヌムが産生するコンパクチンとアスペルギルス・テレウスからえたメニボリン(ロバスタチン)は、ともにきわめて有効なコレステロール低下剤として有名で、緑膿菌培地から分離したドパスチンは抗高血圧剤として有望である。とにかく、これらははじまったばかりの話である。
1950年代の薬の洪水は化学者たちの才能と、有効性が高いか耐容性が優れた誘導体を創ろうとして、既知の化学構造を系統的に修飾する「分子ルーレット法」で、運に頼ることが多かった。こうしたゲームがつづいている。期待した成果がえられるが、薬学革命の第二の波はまったく新しい研究法にもとづくことになるだろう。ここ数年間は正確なメカニズムを解明して、生化学過程の阻害法が設定できるように注意が払われている。ヘビの咬傷による疼痛のように、多くは逸話的な観察で特異的な酵素阻害剤の合成(動脈性高血圧症の治療にきわめて有用性が高いカプトプリルとその誘導体の例)が生れた。アラキドン酸カスケードの系統的研究で、抗炎症剤の作用メカニズムがよく理解できたが、トロンボキサンに対する特異的阻害剤の合成と試験の糸口がみつかり、血栓症の予防と喘息治療用の新薬ができる可能性がでてきた。
その他の分野では疾病の進行で重要な働きをする酵素を同定し、それが新しい治療法をもたらすものと示唆されている。これは仕事が手に負えなかったり、工業的化学合成が採算の問題で壁にぶつかり、予想外の副作用で開発が妨害されるので、おそらく危険な方法だろう。新薬の合理的な設計は大きな抵抗に会うこともあるが、計画によっては実施し可能な状態を示す程度に成功している。
ガンマー・ビニルGABAは、GABAトランスアミナーゼを不可逆的に阻害して、中枢神経系に治療効果を現わす薬である。αジフルオロオルニチンは、細胞の成長に対する役割は不明だが、必須な役割をもつポリアミン類の合成阻害剤である。これらは最近になって認められた開発中の例である。
したがって、薬理学の近未来が店内に陳列する成果は、少なくとも現在のように明るいと予想できるが、逆にコインの裏側にならないとは断言できない。現在の薬の開発に関する知識と研究方法を使えば、サリドマイドやトリパラノールの惨事はさけられただろう。しかし、薬の安全性がすべて研究と開発だけにかかっていると考えるのは危険である。むしろ安全な薬の誤用が悲劇的事件の原因である場合が多い。優良な薬はまちがいなく治療学を変えるだろう。しかし、患者が医療を神話化したり、あるいは医師が治療学を軽率に取り扱えば、医療は前進を止めてしまうだろう。
|