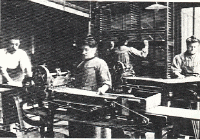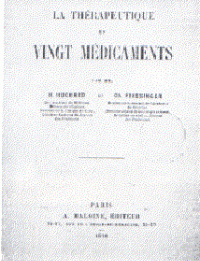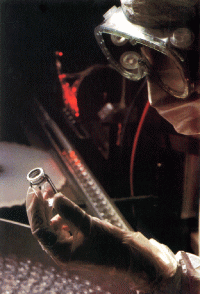|
1914年当時、伝統的な医師は本書のはじめの章で登場する薬用資源が利用できた。しかし、こうした資源の価値は疑わしい場合が多い。なかには、キニーネやベラドンナなど多数の植物薬、甲状腺など臓器を粉末にした動物薬、鉄やイオウなど無機エキス剤もあった。自然が疾病との闘いに用意したこのような天然物だけでなく、前世紀まで無名だった薬もある。19世紀以後、医師は体内の特異的な薬理作用と薬の分子構造の相関について知識を受けつぎ、実験室で普通の方法を使って薬を探索した。前世紀末より催眠剤、鎮痛剤、解熱剤など症状を抑制する作用をもつ新薬が製造できるようになった。また、前述したエールリッヒの業績により、病因に対して化学療法を開始することができた。
20世紀の初頭に医学界と世俗の思想家は、薬物治療の可能性に大きな期待を寄せた。パラケルススが提唱した目標は手元に近づいてきた。パラケルススの夢であった実験の成果を治療に生かすことが、現実のものとなった。
各疾病の特定薬に関するパラケルススの見解は立証された。医師は自然が提供できない新薬を思い通りに創るようになったので、治療行為では「神の僕」であるよりも「神の補佐役」となった。こうした理由から薬物療法がもつ可能性は大きな期待となった。1914年以後に経験してきたことだが、この希望や期待は質・量ともに非常に豊かな薬品庫となって実現した。この豊かさは当時の楽観的な予想さえ上回るものであった。こうした発展を確認するには、現代の薬理学の業績と1910年に発表されたハッチャーの論文『20種の薬剤による治療』を比較すべきだろう。たとえばエリル教授の章では、20世紀における薬理学を俯瞰している。プロメテウスはボキッと鎖を切断したようだ。パラケルススの夢は事実となったが、まだ解決すべき問題も多く残されている。薬理学の発展が新たな混乱を招いたが、伝統科学と同ように惹きつけるものがある。
現 代 の 薬 物 治 療 学 に 関 す る 問 題 点
第一次世界大戦後に薬理学が発展したが、主要な分野に関する簡潔な評価は、現代の薬学が手にした力のよき指標となる。しかし、ライン・エントラルゴ教授が指摘するように、その力はこの領域だけに向けられたわけではなかった。膨大な業績はわずか一世紀前までは想像もできなかったし、多くの可能性が広がり、多方面にわたって薬学の力が高まった。モデッルは20世紀を「薬理学の爆発」と呼んだ。しかし、薬理学のみごとな概説のなかで、現代の薬物療法に問題があると考えて調査するのも適切であろう。
薬学は広範囲におよぶ疾病や病因と対峙して発展し、また鮮やかに成功した。そして薬学は全能性を発揮し、またあらゆる健康問題が薬学を頼りにするとの見方が一般的となり、薬学は大きくかつ有用な武器庫を備え、速やかな寛解をもたらした。こうした事実により薬物療法が大へんに進歩したと評価されたが、本来この見解は真実から離れている。
現代社会は事実を歪曲して、また誇張した立場から万能薬を信じさせ、あらゆる健康障害がそこそこで、それほど重大でなければ薬物療法の需要が増加する要因となっている。否定的な現象がないときは、少なくとも検討すべき問題である。今日、薬は工業製品の一部となっている。これを前向きに捉らえて薬剤費を安くして、多数の患者に使えるようになった。しかし、同時に薬は消費社会の活動や社会の緊張状態に影響され、さらには経済の対象や激しい商業上の競争に組み込まれてしまった。
ここでは、再考すべき諸問題をとりあげ検討してみよう。薬に対する社会の要求が増えることが、果して正しいことなのだろうか。信頼できる健康法や食習慣が決っていたり、健康をそこなわないライフ・スタイルが実践されている場合には問題とならないが、薬物療法に解決が求められることが多いのではないだろうか。新しい薬は社会やその一部門の期待に応え、必需品として客観的に考えて開発されている。薬が無秩序に増加しても、それに比例して全身の健康状態は必ずしも改善していない。この点は記憶にとどめておくべきである。極端な場合、産業が興味をもたない領域は、無視される可能性さえある。「希用薬」は商業上は関心が低いので、製薬会社は魅力を感じないようだ。こうした現象がアメリカのFDAなどの管理庁に、希用薬の商業化計画を促進せる契機となった。同じ見解からWHO(世界保健機構)が何度も繰り返し、各国にWHOリストに準拠した必須医薬品リストの作成を勧告するのも賢明だと思われる。必須医薬品リストに未収載の薬は、表面的な解釈よりも多くの意味があるので、ただちに不適格な薬だするのは間違いだろう。WHOがこの勧告で意図したのは、薬の製造と商業化が需要と供給の法則だけで決まるのではなく、地理的・社会文化的・人間的な需要と保健政策にも対応させることであった。
さらにこの問題をつづける。現代の薬理学が治療上有効だとする薬は多いが、これらがすべての患者に広く同等に作用が発現するだろうか。残念ながらそうではない。各生体いや個人といったほうが適切であるが、薬の摂取法がそれぞれ異なっているし、つまり吸収と治療反応という薬物動態学や薬力学に個人差がある。さらに薬に副作用があっても少ないが、二次作用の軽重は多様である。二次作用にも個人差がある。二次作用が発生したとき、たとえば用量の過誤、知識の欠如、主作用・二次作用・副作用の管理不足、治療中の特定患者に有効な薬を処方できなかったことなど、医師による薬の不適正な使用で患者に障害が起こる可能性は否定できないであろう。患者の過敏症、使用薬への抵抗性と耐性の可能性はきわめて重要である。多くの医師に薬の適正使用をすすめるために、臨床薬理学という専門分野が力強く復活している。
本来は治療効果がない薬を患者に投与して有益な作用が観察される、いわゆる「プラセボ効果」は、私たちの時代の成果ではない。フーパーの医学辞典(1811年)では、プラセボ効果を「疾病を静めるための処方薬」と定義している。1937年にこの作用に関する実験がはじまった。現在では、ある条件下で治療効果がない薬でも、実際に投与した患者が薬の薬理作用を堅く信じていれば、その作用が発現するとされている。薬に治療効果があるとすれば、その作用を患者が信じれば強まるだろう。薬が社会的に名声をえ、患者が医師を信じることでこのような信頼関係ができあがった。一方、患者が薬の効果を疑問視すれば、投与した薬の治癒力が低下して治療効果が変化する。ライン・エントラルゴ教授が最初にプラセボをとりあげたとき、「患者を説得して同意がえられれば、その場合だけ治療が有効だ」というプラトンの言葉を引用している。また、プラトンは「患者の協力が不十分だと薬が無効になる」と教えている。この事実を認めることで、投薬に影響する心理的因子が、現代の薬理学論文で詳細に検討されるようになった。結局、こうした諸因子が薬の臨床研究に関する方法論で重要な役割を演じた。
こうした諸問題は現代薬理学の姿に影を落とすだろうか。問題にならないといえる。成功は自明の理である。しかし、成功のおかげで将来、解決しなければならない問題に直面するとともに、これまでの成果を控え目にかつ客観的に評価することになる。
薬 物 治 療 学 の 展 望
薬物治療学はその可能性を十分に活用しきっていない。その一方で今日では、新しい有用な器具や設備を整っている。質量分析計、ガス/液体クロマトグラフ、安定同位体の標識、ホルモンのラジオイムノアッセイ法、コンピュータ支援などの資材が薬理実験を大いに発展させ、いままで解明できなかった生物医学の事象研究を可能にした。分子生物学、生化学、遺伝子学の進歩が免疫機構の知識を増やし、新しい実験法を構築する基礎として役立っている。こうしたことが転移因子や抗阻止ワクチンの使用で起こり、免疫薬理学の領域で大きな可能性を開拓した。また、新しい知識の泉である研究対象には、現在大へんなエネルギーを費やし集中させている。細胞受容体の発見とその果す役割について述べてみよう。
多数の身体機能を調整するプロスタグランディンの使用、麻酔や精神障害の分野で新しい可能性をもつエンドルフィンとエンセファリンの発見、ある疾病を治療する目的で使うインターフェロンなどみな有望である。これらは薬物治療学の近い将来の展望が、拡がっていることを雄弁に物語っている。
薬 物 治 療 学 の 未 来
生物医科学での進歩が示すように、薬物治療学の可能性は将来大きな希望となっていく。前述した制限により、今後薬理学研究が解明しなければならない問題も残されている。あらゆる分野での研究目標は、最大の効果と最小の二次作用/副作用、最小のコストをもつ現代の薬を探求することである。
WHOが指摘するように、各国の必須医薬品の選定を効果的に継続しなければならない。薬の不適正な使用にもとづく有害作用をさけ、最終的にはプラセボ効果の機序を解明すべきであろう。これら諸問題に関しライン・エンテラルゴ教授が指摘しているように、現代医学に確実に適合する普遍的な治療学を精巧に仕上げる必要性がますます明らかになっている。「人間の行為と人間関係に関する実験薬理学、薬物測定法、臨床薬理学、外科治療学、精神療法の知識、医療社会学、心理学、神経生理学、生化学の専門分野が科学的に共存する」、言い換えればライン・エンテラルゴ教授が「全人類学的な治療学」と呼ぶ専門分野である。
|