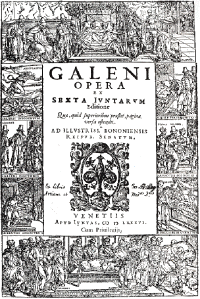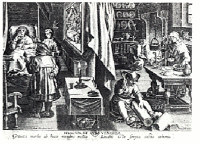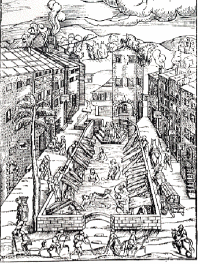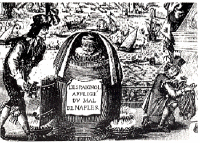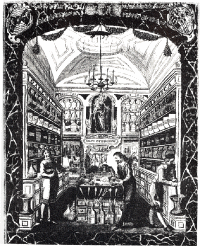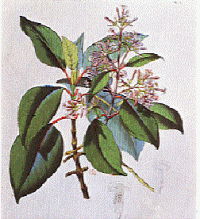|
�@16���I��17���I�Ɉ�t�͎��a�Ƃ̓����ŐH���A�O�ȁA��Ƃ���3��̓`���I���Ö@�����p�����B���̐��I�̈�t�͂ǂ�Ȗ�i�Ƃ��ɐA����j���g���Ă������낤���B�{�_�Ŗ��炩�ɂȂ�悤�ɋN���A���̕���ɂ́A�������w�l����`�A����@�̔����A�ߑ�A���w�̔��W�A�ÓT����̎��������A�M���V����ƃ��e���ꂩ��̒��ڂ̖|��A�����ċߐ��l�̒T���̐��ʂł���n����̑唭���Ƃ������A���̎���ɂ������A�̏o�����ɉe�������B
�@
�` ��
�@����ߑ�I�Ȏp�ɂ������̗v���́u��w�l����`�v�ƌĂ�A�ÓT����̎������������銈���A�M���V����ƃ��e����̒��ږ|��A�Ñ�̈̑�Ȉ�Ƃ����̒m���̉���A�]�_�⒍�����ڂ������Ђ̏o�łł���B
�@���C���E�G���g�����S�����͌��݂ɑ���s����A�ߋ��������ʼn��l�������Ƃ��鋽�D����A��w�l����`���N�����Əq�ׂĂ���B�����O���̏I���10�N�ȍ~�A��w���������t�Ȃǃ��[���b�p�̕����l�����́A�`���I�ȌÓT�̒��҂����{�̌��ł��邱�Ƃ�m���Ă����B�����̌ÓT���̓A���u�̉���҂��o�R���āA�����̃X�R���w�҂��|���B���̂悤�ɓ�d�̎���o���|��́A���e���Ȋw�I�ɓK�łȂ����Ƃ�����A�����l�����͈̑�Ȉ�w��Ɓi�q�|�N���e�X�A�K���m�X�A�v���j�E�X�A�f�B�I�X�R���f�X�Ȃǁj�̒����ɒ��ڂ����邱�Ƃɂ����B�ÓT��Ƃ����ږ|�邱�ƂŁA���e���ς�Ȃ������̏����ȋ�����Ƃ���ǂ����B�ÓT����|��E�����E�������傫�ȑg�D�������������B
�@���Õ���ł͂��̉^���̂������ŁA�M���V���E���[�}�ɂ������u�A���W�{�W�v�̕����ł����ꂽ�B�e�I�t���X�g�X�́w�A���j�ƐA���N���x���f�B�I�X�R���f�X�́w���x�����̑�\�ł���B16���I�Ƀf�B�I�X�R���f�X�̒���ɊȌ��Ȑ}�������āA���������łȂ����e�����M���V�����7��o�ł��ꂽ�B�f�B�I�X�R���f�X�y������̂Ɉ�Ԋ�����Ƃ́A�s�G�[���E�A���h���A�E�}�b�`���[���i1500-1577�N�j�ŁA�C�^���A�ł�17��o�ł��ꂽ�B�ҏW�̐����͎��̍����ؔʼn�ƐV��������ɂ������悤���B����͂��낢��ȏꏊ�̖Ɋւ���}�b�`���[�����g�̌����Ɛтł������B�l�I�Ȍo���ł����m�����L���A�ߑ�I�Ȉӌ����q�ׂ�����������B�����悤�Ȓ�����|���g�K���l���A�}�c�X�E���V�^�k�X�i1511-1568�N�j�A�X�y�C���l���A���h���A�E���O�i�i1511-1559�N�j�A�h�C�c�l�����@�����E�X�E�R���f�X�i1515-1544�N�j���o�ł��Ă���B���w�j�ɐV����������J��������@�̓o��ɂ��A��w�l����`�҂̒����͑����ɕ��y���A���̌��ʈ�w�o�Ŏj�ɂ��Ă��傫�ȉe�����������B���Ƃ��A�Ñ�M���V���ƃ��[�}�̒���͖|��A�_�]�A�������āA�S�������Ă���ǎ҂̌����ɒ��ꂽ�B��w�l����`�҂�������������ɂȂ���āA���[���b�p�̈�������ؔʼn���g���Ė̕W�{�W�s�����B�A���u�̍�Ƃ̒�����o�ł���A���X�G�N�́w�����W�x�ƃA���B�Z���i�́w��w�T���x���ĂэL�܂����B
�@
�V �� �� �A �� �W �{ �W
�@���[���b�p�̈�t�����́A�ÓT��Ƃ̒���ږ|���łɐ}�Ɖ���𑽗p�����B�����̃��e����ƃA���u��̒������L�p�ł������B�������������͌��ݏo����Ă���w���x�̏�Ƃ��Ė𗧂��Ă���B���l�b�T���X�̐l�X���w���x�̉��l�����߂�̂ɑ傢�ɍv�����Ă���B�ߐ��̈�Ƃ͐A����Ɋւ���m����|��A�����A�_�]�A��������ƂƂ��ɁA�A�����L�͂ɂ킽���Ē������A�V�����A������̏W������u�V�����A���W�{�W�v�ւ̓o�^�����R�ɍs�����B
�@�Z�p�ʂƂƂ��ɓ�̊�{�I�ȕϊv���A���̐��I�ɂ�����A���w�̐i�����x�����B�A�������ɋ���œK���Ȉ��͂������ĕۑ����A�d�����ɍL���ēW������悤�ɂȂ����B�W�{�A���͒����ΏۂƂ��ėX�ւŌ������\�ɂȂ������A���ω��̂܂܂̐A���̓������͂����肵�Ȃ��Ȃ����B�{�@�����`�A�E�M�j�[�i1490-1556�N�j���̗p�����y�����B���̕ϊv�͐A���W�{�W�ɐ}���ڂ������ƂŁA�������W�{���璼�ځA�A��������ꍇ���������B�I�b�g�[�E�u�����t�F���h�i15���I���|1534�N�j��L.�t�N�X�i1501-1544�N�j�̍�i�������悤�ɁA16���I�̖ؔʼn�͎����ɐ����ʂ��Ŕ������A�A���̓����������قǎʎ��I�ɕ`����Ă���B���̎����̍ő�̌�����A���h���I�E�Z�����s�[�m�i1519-1603�j�́w�A�����i1583�N�j�x�ŁA���ڐA����1,500��ł������B����A���ށA�����Ĕ���Ɛ����ɂ��ĉ�����Ă���B15���I�ɂ͔M���I�ȍ̏W�Ƃ����A����100�N�Ԃɂ͍ō��̐����ɒB���A�K�X�p�[�E�{�[�C���i1560-1624�N�j��6,000��̐A���ނ��Ă���B
�ߐ��̐A���W�{�W�̑����́A�h�[�G���X�i1517-1585�N�j�̒���̂悤�ɕʖ��A�A���w�I�����̉���A�����ꏊ�A���Ì��ʂ��L�ڂ��Ă���B���̐V�����A���W�{�W�́A�e�I�t���X�g�X�̐A�������������i���̂悤�ɁA�����̐A���w�̔��W�Ɩ��ڂɊW���Ă����B13���I�̃��[���b�p�ł́A�����̏C���@�ɂ��������ƈق��Ă����B��p�A�����̊�b�ƂȂ����뉀���J�X�e���k�[�{�ƃT�����m�ɂ������B���l�b�T���X����͓����̎��W�Ƃ̌X��������ŁA�܂��ٍ�������o���邱�Ƃ������ĐA���������s�����B�㗬�K���̐l�����ٍ͈���ʼn��������瓮�A�����W�߂�悤�ɂȂ�A�o�b�N�n�[�h�́u���E�Ɛl�ނ̔����v�̌��t�ɍ����āA�ς������Ԃ���肾�����悤���B���̂��߃��l�b�T���X������A���������������B���c�j�R���X�W���i1447-1455�N�j���ŏ��Ƀo�`�J���{�a�ɐA�������J�݂����B�k�C�^���A�̏��s�s�ł̓s�T�A�p�h�A�A�t�B�����c�F�A�{���[�j���ɂ��̎�̒뉀�����������Ƃ��킩���Ă���B���̃��[���b�p���s�s�ł��A���C�f���i1577�N�j�A���C�v�`�b�q�i1579�N�j�A�����y���G�i1592�N�j�A�p���i1598�N�j�ɐA�������J�����Ă���B�����A��w�����͐A��������̏W�����A�����g���Ė���u�`�����B�P��܁i�P��̐A����j�������E����Ð��w�Ȃɑn�݂��ꂽ�B�ŏ���1533�N�Ƀp�h�A��w�ɂł����B�q�C���ɔ��������A�����̂����ǎ��Ȃ��̂��A���������A�����ŏ�������悤�ɂȂ����B�A���̂���������́A���Ƃ����g�E�����R�V�A�W���K�C���A�}���A�p�C�i�b�v���A�q�}�����̎�q�͉h�{���������L�p�ł������B�C�g�����A�g�P�C�\�E�A�A�T�K�I�Ȃǂ͑����p�Ƃ��ĉ��l���������B�V���E���炠������̂�����Ă����B���̑��ɂ����m�����i�X���`���[���b�v���n�����Ă���B��p�A���͂₪�Ĉ�ԍ����ɂȂ�A���E��ƂƂ��ɉ��l������A�A���n�Y�̍ō��̏��i�ɂȂ����B��p�A���������y�����B�Z���r�A�ł�16���̒����ɁA�j�R���X�E���i���f�X�A�V�����E�g�[�o�[�A���h���S�E�U�����m�A�t�@���E�f�E�J�X�^�l�_�����L���鎄�c�̒뉀��������
�@
�V �� �� ��
�@����������������16���I��17���I��2���I�ɁA��̎�ނ����ɑ����Ȃ����B���[���b�p�͌��m��ʐA���̐V���ȎQ�������}�����B��q�C�Œn������ړ����Ȃ���V�����A���������B�����̖�͊�{�I�ɋɓ��Ƃ̒ʏ��ő�ʂɓ��肵���A���h���A������������m�̖����������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����������͖f�H�ɂ�����s�s����̒���҂ɂƂ��āA���ɏd�v�ȏ��i�ł������B��⍁�h���̓C�^���A�ƃh�C�c�̋�s�Ƃ��Ǘ����A���̎���Ŕ���ȗ��v�����Ă���B
�@���m�ւ̊S�Ɩ`���S�����������l�b�T���X�̂��炵�����s�Ƃ�������藧�Ă��傽�铮�@�́A�����V�N�Ȗ�ƍ��h����������V�����ʏ��H���݂��邱�Ƃł���B�R�����u�X�����������V�������C���h�����́A�X�y�C�����ɋM���������łȂ����h���������^������̂ƍl����ꂽ�B���@�X�R�E�_�E�K�}�͒n���C�̍`�p�s�s���o�R��������܂ł̍q�H��ς��A�͂��߂Ċ�]��̍q�H���J�����č��h�����^�B
�@�X�y�C���ƃ|���g�K���͐V�����f�H�������B���c�̑咺�����J�������ٌ������B���̒����Ń|���g�K���͓��C���h�����i�u���W�����͂��߃G�`�I�s�A�A�A���r�A�A�y���V���A�C���h�j���l�����A�X�y�C�������C���h�����̊J�������F�߂�ꂽ�B���̂悤�Ƀ��X�{���̃C���h�ق��������|���g�K���ƁA�Z���r�A���ق����Ă��X�y�C���́A�����b�J�����̊J�������߂����ĕ��������������̂́A���m�Ɛ��m�̖f�ՂɍD�K�ȏ���߂�Ɏ������B�鍑�̋�s�Ƃ͌o�Ϗ�͋��E��̑D�ׂ���ԏd�v���������A�A����̐ωׂ��Ǘ�������@���s���Ȃ��Ƃ��킩���Ă����B�X�y�C�������͓����A�ŏI�I�ɐV���E�Ƃ̖f�Ղ�Ɛ肵�Ă����h�C�c�̋�s�Ɓi�Ƃ��Ƀt�b�K�[�ƃ��F���T�[�j�ɑ傫�ȍ����������B�X�y�C���ƃ|���g�K���������e���̓��F�l�`�A��A���u�ƏՓ˂��A���̈���ŃC���h�����Ƃ̊C��f�Ղł̓h�C�c�A�t���}���A�C�M���X�̉�������B���ǁA���R�f�Ղ����������B�M�����A�A����A���̓Ɛ�͏I���鍑�͕����B
�@�X�y�C���̓��F�l�`�A�̌��͂𗊂�ɁA���m�̍��h���ƐA�������ɓ���Ă����B�X�y�C������Ԗ]�K���i�͖�ł������B���h���͐H���̖��t����ۑ��ɋ����邽�߂ɋ��߂�ꂽ�B�R�����u�X�͑�ꎟ�̗��s��A�V���E�ɂ��̂悤�ȕ��Y������ƕ��āA�J�^���j�A���̃t�F���f�B�i���h�ƃC�U�x�����h�������B���Ə����͐V�����̓y�n�ŎY���鎩�R�̕x������ړI�ŁA��̉����ɃZ���r�A�̈�t�A���o���X�E�`�����J��h�������B�C�O�ւ̍q�C��������O�ɂȂ����B�x���i���W�I�E�f�E�T�[�O���A�j�R���X�E�t���S�X�A�t�����V�X�R�E�w���i���f�X�A�t�F���i���f�X�E�f�E�I�r�G�h�A�z�Z�E�A�R�X�^���������������̔N��j�Ƃ���҂́A�A�����J�̐A�����ɂ��ċL�^���Ă���B
�@�V���E�ł̓��L�V�R�̖�ԖL�x�ł悭�������ꂽ�B�t�����V�X�R�C������x���i���W�I�E�f�E�T�[�O�����t�����V�X�R�E�փ��i���f�X�͋����ł��̎d���ɂ��������B�w���i���f�X�́w�V�X�y�C���ɂ������̕�Ɂx��4,000��̐A�����L�ڂ��A����1/3�ɂ��Ė��́A�ʖ�
�A�O�ρA���Ï�̓����A���ÑΏێ����A����ꏊ����������B�V���E�ɂ͐A������g�p�����\���ȓ`�����������B���n�l�̈�t�}���`���E�f�E�N���c���������A���W�{�W�w�C���h�̖ژ^�i1552�N�j�x�ƁA���N�e�Y�}�c�邪���L�V�R�V�e�B�[�ʼn^�c�����A��������A�A���L�x�ł��������Ƃ��킩��B
�@�V���E�̐A�����������A���Ӓ�p�̎w�j�Ƃ��Ďg�����߂ɁA���[���b�p�̐A���W�{�W���K�v���Ƃ����������܂����B�A�����J�̖�����[���b�p�ɏЉ��͂��߂��B�j�R���X�E���i���f�X�i1493-1588�N�j�͐V���E�Ɉ�������ݓ���Ȃ��������A�����̏ꍇ�A�ނ̂������ŐA���̒m�����L�����B
���i���f�X��2���̒����̂����A1���́w���C���h�Y�̈��i�x��1565�N�ɃZ�r���A�ŏo�ł���A1569�N�A1571�N�A1574�N�1580�N�ɍĔł��ꂽ�B�t�����V�X�R�E�Q�b���͂�����ւ�ڍׂɌ������A�������Ƃ���邷�ׂĂ̍��̌��t�ɖ|���B���i���f�X�͓����A�Z�r���A�̈�t�Ƃ��ėL���ŁA�����ɐV���E�̖f�Ղɂ��[���֗^���Ă����B�ނ͒����ŃC���f�B�A���i���C���h�����̌��n�l�j�́A�z����ƐA������̗p���Ă���Əq�ׂĂ���B���������̏����ǂɂł���J���V�E�����a���ŁA�ŕ��̉�ō܂ƍl�����Ă����ݐ����A�����̍z����̂Ȃ��ɂ݂������B���i���f�X�͂܂��l���A�Ζ��A�R�n�N�A�C�I�E�A�S�ɂ����y���Ă���B�܂����[���b�p�ɒm���ĂȂ������쐫���唞�A�����b�p�A�T�b�T�t���X�A���łɃ��[���b�p�ɏЉ�ꂽ�^�o�R�A�V�i�����A���\�E�{�N�A�o���T���ȂǍŐV�̐A���A���Â�H���ɏd�v�ȐA���Ń��[���b�p�ɓ���ݐ[���g�E�����R�V�A�p�C�i�b�v���A�s�[�i�c�A�q�}�A�T�c�}�C���A�T���T�ȂǃA�����J�A���̉���̓��i���f�X�ɕ����Ă���B
�@���[���b�p�ɗA�����ꂽ��̑����͌��ǁA��������Ƃ��ꂽ���É��l�͂Ȃ������B�^�o�R�x���h�i�W���A���E�f�E�J�X�g����i���f�X�̓^�o�R�����ɁA���ŁA���ɁA�b���A�ݒɁA�𒎁A�ǂɎg����ƕ\���j�ƁA�ᔻ�h�i���C�o�ƃA�M�����[�̓^�o�R�̗��p��ᔻ����ƂƂ��ɐl�ɂ͗L�Q���Ɣ��j���Η������̂���L�̗�ł���B�`���R���[�g���R�[�q�[�ł��������Ƃ��N�����B�`���R���[�g�͈݂̓��������������a��u���ɂ���Ƃ����A���̂��߉��ɏ������ꂽ�B�R�����l���E�f�E���f�X�}���́w�`���R���[�g�̓����Ǝ��x���A�`���R���[�g�Ƃ��̎��ÓK�p���x�����������̗�ł���B�x���h�Ɣᔻ�h�̑Η��̓R�[�q�[�̎��Âւ̓K�p�ł��p�ɂɐ������B�x���h�̓R�[�q�[���ْ��������炵�A�������t�z��p��L����̂Ŗ��C�A���C�́A�S�t���ɁA�܂��������ɂ��L�v���Ǝ^�������B�R�[�q�[�_�c�ɂ��W���A���E�^���I�[���̒����w�N�w�I�ɓ��_���A�N�z�̈�t����������ŁA�����̈�t�̂��߂ɂȂ�A���O�̕ی��ɗL�v�ȃR�[�q�[�E�j���[�X�i�o���h���b�h�A1692�N�j�x���C�V�h���E�t�F���i���f�X�E�}�`�G���]�́w�R�[�q�[�̎��Âւ̓K�p�ɔ��F�g�̓I�E��w�I�ɓ��_���A�N�z�̈�t�Ɏ^�����āA�����̈�t��Ⴂ��t�ɉ���i�}�h���b�h�A1693�N�j�x������B
�@���[���b�p�Љ�ł͕ی���肪�傫���Ȃ��Ă����̂ŁA��ԂɊ��Ē����l�C�����������i�͗L���Ȗ�ł������B���̑�ꂪ���\�E�{�N�œ������[���b�p�ł����Ƃ����s�������ꂽ���ɂ̎�A���Ȃ킿�~���ɗL���Ȗ�Ƃ��ꂽ�B�������A�~�ł̌�������t�Ɨ��j�Ƃ����������̂�16���I�Ȍ�ł���B1495�N�ɃX�y�C���R���i�|�����͂����Ƃ��A�t�����X���̊ԂŔ~�ł����s�����B�t�����X�����A�����Ă���A���̎��a�����[���b�p���ɍL�������B�~�łɂ͂��낢��Ȗ��̂�����ꂽ�B�t�����X�l�̓i�|���a�A�C�^���A�l�̓t�����X�a�A�X�y�C���l�̓t�����X�a�Ƃ����A���邢�̓K���A�a�̂悤�ɗ��j�I�ɑ嗬�s�����ꏊ�Ɉ���ŌĂB
�@�`���a�̖����ŕa���𖾂̓w�͂��h������A��ւ�Ș_�����������B�Ȃ��ł����ڂ��ꂽ�c��͈꒼���ɕ��f���A���N�ȏ����ƃn���Z���a�̒j���̐��I�ڐG�A�V��....�ł������B���̓I�ɏǏ�͔畆�Ɍ�����̂ŁA�����Ŏ��{��������̓h�z���o���I���Ö@�Ƃ��Đ������ꂽ�B�W���A���E�f�E���B�S�i�W���o���j�E�_�E���B�S�j�������p�������B����͑�ւ�ɐl�C�������Ĕɗp����A18���I�܂Ŏg��ꂽ�B����͋��͂��������Ŗ@�Ƃ��Ă��g�p���ꂽ���A���ł̊댯�����������B���҂��C���A�b���i���b�j�A�R���̎��������߂ĊW����������M�̂Ȃ��ɁA�����̓������ď��ł����B���̕��@�͒��ł̊댯�������ւ�|����ꂽ�B���̂����ɁA�~�ł͐V���E����������܂ꂽ�Ƃ̐����x�������悤�ɂȂ����B���C�X�E�f�B�A�X�E�f�E�C�X�����_���w�X�y�C���������炫���A���ȕa���������Ȃ���i1539�N�j�x�̂Ȃ��ŁA�܂��t�F���i���f�X�E�f�E���B�G�h�̓�l���A�R�����u�X�̑D�������̎��a�����[���b�p�ɂ������݁A�X�y�C�������o���Z���i����i�|���ɉ^�Ƃ�����������B�~�ł̃A�����J�N�����͂����x���҂������Ē蒅�����B�������A�X�y�C���l�͐V���E����~�łƈꏏ�ɓV�R��������A���Ă���B���Ƃ��ΐ��Ȃ�i�C���h�����̊ۑ��A���\�E�{�N�j��18���I�܂Ŗ���邩�ۑ����ςĐ��܂Ƃ��Ďg���Ă����B���̐��܂͋ꂭ�F�����ŁA�P��3-4��ɕ����ē��������B������p�A������p�A���A��p���킩���Ă���B�`���L�܂����E�}�`�ƒɕ��ɁA�܂������X�܂��������Ă⎕�ɂɓK�p�����B�t���J�X�g�����g���A1521�N�ɕ|���a�̎��Ìv��̉�ɂȂ鐸������ɏ�����1530�N�ɏo�ł����B�����œo�ꂵ�����@�����[���b�p���ɓ`���A�A���Ɛ茠���A�E�O�X�u���O�̃t�b�K�[��s�̎�ɂ����܂����B�t�����V�X�R�E�Q�b���͓O��I�Ɏ����������A��t���i���f�X�̏Ǘ�ł̓��\�E�{�N�����ۂɌ����Ɨ��ł��Ȃ������B�������A�t�b�K�[��s�͈�t�ɂ������x�����Ė{�܂̎g�p�������߂��悤���B
�@�悭�c��ɂȂ����~�ł̋N���ɂ��āA��w�j���J�[���E�X�b�h�z�t�̓R�����u�X�̑D�����A�����J����A������ȑO�ɁA�����E�ɔ~�ł����݂������Ƃ������������U�a���w�I�ȍl�����܂����Ȃ��痧�����B���̈���ŁA�R�����u�X����������O����A�V���E�ɂ��~�ł����݂������Ƃ��F�߂��Ă���B�t�����V�X�R�E�Q�b�����q�ׂ��u�A�����J�̔������җ�ɗ��s���鐫���̋ǒn�^�E�c�Ɍ^�g���|�l�[�}�ǁi�t�����x�V�A�E�A�����J�[�i�j���A���[���b�p���ɖ����������v�Ƃ������t�����݂̌����ł���B
�@�g�R���ƃL�i��17���I�ɂ͂��߂ēo�ꂵ�Ĉȗ��A���Ï�̐����ŕ]�����悩�����B�g�R�����W�F���[���E���E�|�A�i�s�\�A1611-1678�N�j���w�u���W���̖��i1648�N�j�x�ʼn�����A1672�N�ɂ��̐A�����u���W���ɉ^�t�����X�̈�t���E�O���X�����[���b�p�ɏЉ���BJ.H.�w���x�`�E�X�i1661-1727�N�j�����C14���̑��q���g�R���Ŏ��Â����B���̂��߁A�f�����R�ԗ����Ƃ��ĕ]�������܂蕁�y�����B�@
�@�L�i�̔�����[���b�p�ւ̓��������łȂ��A���Ì��ʂɂ��Ă������̘_�����������B�_���͊�{�I�ɗ��j�Ƃ����̌����̑���ł������B���j�E�ł͈�ʂɁA�y���[�̃C���f�B�A���̓L�i�����M�̎��ÂɗL���Ȃ��Ƃ�m���Ă����Ƃ���ӌ���F�߂Ă���B���n�̉����������y�X�E�f�E�J�j�U���X�́A�閧���݂�1630�N�Ɏ������}�����A�M���L�i��̎U�܂Ŏ������B�ނ͂̂��Ƀy���[�̑��`���`�������݂ɕv�l�̃}�����A�M�����Â��邽�߂ɃL�i�𑗂����B���̌��ɂ��Ă͋^�킵���_������B���Ƃ���
���j�{���Ƀ`���`�������ݕv�l�������̂��A���邢�͎��ۂɃ}�����A�M���������͔̂��݂������̂ł͂Ȃ����B���j1840�N�Ɉ�t�W���A���E�f�E���E���F�K���L�i���X�y�C���ɉ^�сA�X�y�C���̖�ɂȂ����̂������ł͂Ȃ����B1838�N�ɃL�i���X�y�C���Ŕ̔����ꂽ�؋�������悤���B�L�i�ƃC�G�Y�X��̊W���L���F�߂��Ă���B���̌��Ɋւ���t�����V�X�E�Q�b���̌����́A���M�ɑ���L�i�̎��Ì��ʂ̔����ƃX�y�C���ւ̓����ɂ��āA���̂悤�ɐ������Ă���B�L�i�̖̓C���h�����̌��n�l�������Đk����̂�}������̂Ƃ��āA�M���t�ɂ��Ĉ��ގ��������B�C�G�Y�X��̐鋳�t�����̏K�����ώ@���āA�L�i�ɂ͍��i�̗}����p�������Đk�������炷�ƍl���A�ނ�ɃL�i���g���Ċ����Ƃ��ɔM���t�̂Ők����}���A�܂����M��������悤�ɋ������B���̈���ŁA�L�i�̓}�����A�a���́i�}�����A�����j�̕��̂�j�邪�A���ꂪ�{�܂̏nj�w��̍�p�ł���a���w�I���ʂł���B�t�����V�X�R�E�Q�b���̓`���`�������݂̓������؋��ɁA�O���M��늳�����͕̂v�l�łȂ����݂ŁA�L�i�Ɂu���ݕv�l�U�v�Ɩ����������R�͂��̃P�[�X�ɂ����̂��Ƃ��Ă��邪�A�܂������F�߂��Ă��Ȃ��B�����ɃQ�b���̓W���A���E�f�E���F�K���L�i���X�y�C���ɂ����炵�A�Z���r�A�ɍL�܂����ƍl���Ă���B
�@�L�i��17���I�̒������烈�[���b�p���Œm��킽���Ă����B�ŏ��̃L�i�g�p�̋L�^���y�h���E�f�E�o���o�̒���w�O���M�̎����i�Z���r�A�A1642�N�j�x�ł������B�C�G�Y�X��̓L�i�̕��y�ɊW���A���̂��߂ɂ��钇�Ԃł́u�C�G�Y�X��U�v�Ƃ��ėL���ł������B�����̂������ŃL�i�͍����Ȃ��̂ɂȂ����B�������A�L�i��ᔻ����l�������B�Ȃ��ł��v���e�X�^���g�̓��[�}�̐��E�҂��x��������̂͂��ׂĔ��Ȃ̂ŁA��`�ɂ��ƂÂ��ăC�G�Y�X�����������̎g�p�ɔ������B�L�i���Δh�̈�t������A���}�b�W�[�j�A�A���x���`�[�j�A�V�f���n���璘���Ȉ�t���������A�K���m�X�̊w����M���Ƃ��狭���ᔻ�͂Ȃ������B�}�U���[�m�����S�̐��@�����L�i�Ŏ��Â����悤�ɁA���C14�����������̂ŃL�i�̖��������܂����B�L�i�͂���n���Łu���@���U�v�Ƃ��ėL���ɂȂ����B�L�i�̍�p�͓`���I�ȕa�Ԑ����w�ɔ�������@�Ő������ꂽ�B�㉻�w�h�̓L�i�̌��ʂ������ǂ̔S�t�ǂ�n�������p�ƂƂ��ɁA���t�̔M�ŋN����u���y�v�Ƃ��̉�p�ɂ��������Ƃ����B�����A�㗝�w�h�̓L�i�����t����߂��邩�炾�Ǝ咣�����B�L�i�͗L���ł���ƋL�^����L���g�p����Ă������A���N�ɂ킽���đ傫�Ș_�����Â����B���̋c�_�̈ꕔ�̓L�i�̋N���ƃ��[���b�p�ւ̓����Ɋւ�����j�I�Ȗ�肪���S�ł������B�������A�L�i��o���T���̎���Ɋւ��ĐH���Ⴂ������A�L�i�̖̉���ɂ��Ȃ�̊ԈႢ���������B�L�i�͍R�}�����A��p���Ȃ���ʂ̑e���i��������Q�����B���܂�ɂ����ʂ������^�����A�Ǐ�̍Ĕ����p�������B1816�N�ɃS���X��l�ŁA�܂�1820�N�Ƀy���e�B�G�ƃJ���F���g�[���L�i�E�A���J���C�h�����ăL�i�̓��^����w�L���Ȃ��̂Ƃ����B
�@���u�n�̍q�C�Ƃ����傫�Ȗ����������������A�����J�Ŕ������ꂽ�B���H���q�C���郈�[���b�p�l�̏�g���͉a�ɋꂵ��ł����B�`���o�i�R�a���̔z���́j���ܗL����k�A�����J���Y���j�I�C�q�o�ɂ�鎡�Â����̎���ɂ͂��܂����B1564�N�ɃA���g���[�v���o���f�B�E�X�E�����V�F���X�i
1525-1579�N�j���A�a�̎��Â��I�����W���������𓊗^������@���Љ�Ă���B�J�[���E�`�V�E�X�i1524-1609�N�j���N�T�C�`�S�i�A�X�R���r���_���܂ގ��j���D�ꂽ�R�a����L����Ɣ��\�����B�������A�a�̍���͋ߑ�q���w�̑n�n��J.�����h�i1716-1794�N�j�̋Ɛт�18���I�̂��Ƃł������B
�@�V���E�ւ̍q�C�������ߐ��̖���������v���ł͂Ȃ��B16���I�Ƀ��[���b�p�ɓ����������m�̖�̔����Ɠ����́A�|���g�K�����J���f�Ղɂ����̂ł������B���̂Ȃ��ɂ��V���E�K���剩���������B�K���V�A�E�f�E�I���^�i1501-1568�N�j�́A1563�N�ɃC���h�̓`���瑽���̖�����p���āw�P��܂̌����x�킵���B
�ނƃN���X�g�o���E�A�R�X�^�i1525-1593�N�j�̓�l�����m�̖�����ɂ�����\�I�Ȑ��Ƃł���B
�@16���I��17���I�̐l�����͓���̐V�Z�p�ƂƂ��ɁA�V�����A����̎Q���œ����̖���x�����BW.�n�[���F�[�i1578-1657�N�j�������ɂ��ƂÂ��āA���t�z�_������B���t�͂��ׂĂ̑���ɓ��B�����B���������āA�Ö����ɖ�𒍎˂���l�������܂�A�����J.S.�G�V���b�c�i1623-1688�N�j�����s�����B�ނ�R.���[���[�i1631-1691�N�j�̗A���\����m���Ă����ɁA�l����l����уC�k���u���A�����s�����B�������A���̗A���Ō����s���̎������������悤�ŁA�����͒��~�ɂȂ����B�A���̓����h�X�^�C�i�[�����t�^�s�K�����𖾂���܂ōĊJ����Ȃ������B17���I�ɃX�C�X-�h�C�c�l��J.J.���F�b�t�@�[�i1620-1695�N�j���z�~�J�A�^�o�R�A�h�N�j���W�����g���Ē��Ŋw�̎����������B���ڂ��ׂ��ł���B������̃A���J���C�h�̓X�g���L�j�[�l�A�j�R�`���A�R�j�C���ł���B�V���g�[�N�ƃt�H���^�i�͖�̊��������肵�Ă��邪�A���F�b�t�@�[�͔ނ�̂悤�ɐ������Ȃ������B�������A���Ŋw�̎������͂��߂Ċ�{���܂̐��������ނ��A���Ŋw�I�Ȑ����Ɍ������āA19���I�O���ɂ̓}�W�����f�B�[�ƃI���t�B��������ɔ��W�����A�N���[�h�E�x���i�[�������������B���̂悤�ɖ��16���I��17���I�ɔ��W�����B���͂Ő������邪�A�z����͂��̏͂ŏq�ׂ��悤�ɁA���̎���̎��a�̎��Âɏd�v�Ȗ������ʂ����B
|