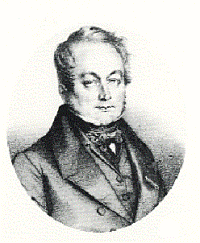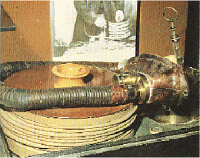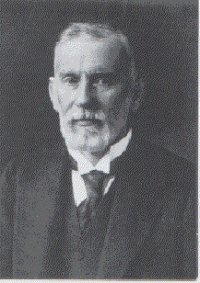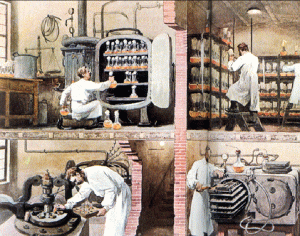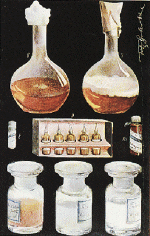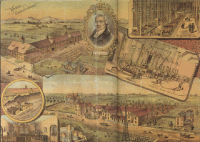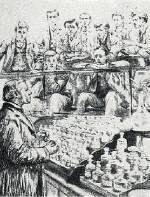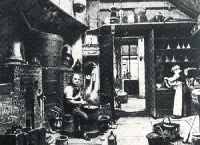|
ロマン主義時代の非外科的治療は、相反する二つの重大な事項で完結する。一つはスコーダとダイエトルの治療ニヒリズムで、薬の利用に厳格な立場をとる考え方を代表している。もう一つはマジャンディーの生理薬理学、オルフィラの毒物学、アルカロイドの化学分析、リービッヒの生物化学、統計学を応用した証明法といった科学の成果である。日常経験や単なる推測と異なり、科学を基盤とした本物の治療知識の登場に期待が高まった。本章では科学的な薬理学、新薬の化学合成、実験にもとづく治療の3項目を述べるが、1848年から1914年の薬がこうした期待の実例となるだろう。
薬 理 学
薬の実験的研究を専門とする大学の学部創設で、19世紀の薬理学と自然科学の関係が制度として確立した。このした方向は1844年にカール・グスタフ・ミッシェリッヒ(1805年〜1871年)がベルリンで薬理学教授に就任してからはじまった。ミッシェリッヒはマジャンディーの動物実験とともに化学を応用し、多数の薬と毒物(酢酸鉛、硫酸銅、鉄製剤、利尿剤、硝酸銀、エーテル油、酢酸、ホウ酸、シュウ酸、クエン酸、酒石酸など)の生物作用を研究した。『薬剤学教本(1837-1846年)』が広く読まれていた(1876〜1861年に3巻が再版)。
彼は1845から1867年にドルパットで、また後年ギーセンで教授になっている。自宅で行った独創的な研究のおかげで、ドルパット大学から解剖学の研究と薬理学研究所の開設という大へんな栄誉が与えられた。リービッヒの記憶がまだ新しいギーセンに招かれたとき、再び自宅の実験室で仕事をしている自分に気づいた。最初の自著はイギリスの医師が書いた『薬理学入門』のドイツ版『ジョナサン・ペレイラの薬剤学便覧(1846-1848年)』で、次いで『ウェーバーの薬剤学諸問題(1849年)』)と『ウェーバーの薬理学研究(1857年)』を出版して、薬理学を実験薬理学の一分科とする権利と必要性を説きながら、伝統的治療学から解放するよう主張した。後年、この考えにエールリッヒが正当な方法で疑問を投げかけたが、ミッシェリッヒの意見は重要であり、また有益なことであった。
ブッヒハイムはドルパット大学の門弟たち(シュミーデバーグもいた)と一緒に、神経筋作用剤、ライ麦角、肝油、ナス科植物の散瞳やアルカロイドのほかに、酸の尿中排泄、発酵過程に作用する薬、フェノールとカンフルの神経系に対する作用の薬力学と体内運命を研究した。彼の著書『薬剤学』は何度も再版されたが、薬を化学的性質と薬力学的性質によって表わそうとした最初の試みである。
カール・フィリップ・フラック(1816−1880年)はブッヒハイムと同時代の人で、実験薬理学を夢に描き、同じ道を歩んでいる。彼はマールブルグ大学を説得して、1867年に歴史的には第2番目の薬理学研究所を開設した。あらゆる点でブッヒハイムが立てた精巧な計画に沿っていた。
実験薬理学には観念的な知識とともに、三つの有用な技術の支援が欠かせない。第一が薬の成分、体内変化、残留物の排泄が測定できる化学技術。第二が科学的な研究がしやすいようにデザインした、臓器や器官系におよぼす薬の作用を変換する記録技術。第三は研究対象の薬と毒物の微妙な陽性反応が検出できる、肉眼的または顕微鏡的手段を使った実験技術である。リービッヒにつづいた生理学者の進歩とともに、ドルトンとベーゼリウスによる一般化学の急速な発展が、論理的な技術を可能にした。ルードリッヒのキモグラフの発明(1849年)やその他各種の記録計(呼吸曲線記録計、脈波計)の急速な出現は、薬理学者にとって第二に必要な条件である。三番目の技術上の必要条件下で、Cl.ベルナールは、筋線維運動装置に中毒作用と麻痺作用を起こす優れた針先の技術を駆使して、クラーレの中毒作用を研究した。この研究はさりげなく実験生理学の可能性を証明した。その後、植物人間の寿命に対する麻酔剤の影響について、優秀な生理学者が行った業績が、実験を基盤に全身を対象とする比較薬理学の可能性を明らかにした。
こうしたすべての考察が、ビンツとシュミーデバーグの二人によって統合された。彼らはブッヒハイムの次世代の人で、19世紀の後半と20世紀初頭10年の間に、近代薬理学の研究を十分に発展させた。カール・ビンツ(1832−1912年)はウィルヒョウとフレイヒスの門弟で、1869年にボンに薬理学研究所を開設。門弟たちと一緒にキニーネ、ヒ素、エーテル油、ハロゲン化合物、麻酔剤の作用を研究した。『薬剤学の基礎(1866年)』は12版に達し、『薬理学講義(1884年)』も大へん成功した。
しかし、私たちが調査している時代の薬理学の泰斗は、オスワルド・シュミーデバーグ(1838−1912年)である。この時期には二つの分野があり、シュミーデバーグが系統的に一本化しようとした二学科にあたる。その一つは正確に考察する薬理学で、他方は生理学と実験生理学である。一度、調査してみよう。
シュミーデバーグの薬理学の業績はドルパットでブッヒハイムの指導を受け、クロロホルムの代謝に関する研究からはじまった。その後、シュトラスブールで研究をつづけ発展させた。彼のみごとな研究論文『ムスカリン(1869年)』は、エストニア時代にトルハート(1869-1870年)と共同で行ったニコチンの研究として実を結んだ。しばらくしてから、ニコチンの心臓と肺胃神経の神経支配におよぼす作用を解析し、全身の自律神経系に関する薬理学(自律神経の肺胃部と交感神経部に対する全身毒性)の研究に着手した。カフェインとプリン体(横紋筋に対する直接作用、利尿作用)に関し、ドルパット(1869年)でのシュミーデバーグの初期の仕事から、その後の一連の研究がまとまった(1874年、1901年)。
ジギタリスと麻薬の研究がとくに重要であった。シュミーデバーグはジギタリス抽出物の活性成分を化学的、薬力学的に分離し、同じ方法でカルバミン酸パラアルデヒドエステルのニコチン作用を研究し、1882年に共同研究者のセルベッロが本剤を治療に使った。1885年に抱水アミレンとウレタンが尿素誘導体の化学療法の道を開いた。薬の化学組成と生物作用の関する正確な知識について、初期の基本を確立した。この問題に対する偉大な薬理学者の頭のなかにある概念は、薬とそれが作用する細胞成分間の分子相互作用(毒作用基との結合に関するポール・エールリッヒ説への露払い)と、分子構造による構成成分の性質(化学物質の確実な薬理作用に備った性質で、基や根の特徴を単純に合計したものではない)の二つである。その後、シュミーデバーグが薬力学の領域で解明したものとして、重金属の局所作用と再吸収作用を整然と実験で区分した研究と、グルコン酸発見の発端になったカンフル問題がつづく。実際のところ薬の革新的な研究の大部分は、シュミーデバーグや門弟が行ったといえるだろう。みごとな手引書『薬剤学摘要(1883年)』は1914年まで7版が発行された。重要な定期刊行物でクレブス、ナウイン、シュミーデバーグが創刊した『実験病理学と薬理学紀要(1872年)』は、結局最後はナウインとシュミーデバーグが刊行した。
少し遅れたが、イギリスの薬理学も明るく輝いていた。主要な人物は以下の通りである。バースロミュー病院の教授でスコットランドのトーマス・ラウダー・ブラントン卿は、ジギタリスや蛇毒の作用、白血球核の化学、化学構造と生理作用の関係、心臓に対する肺胃神経の作用を研究するだけでなく、冠静脈と冠動脈の双方に拡張作用をもつ亜硝酸アミルの発見で有名である。彼は研究論文『医薬品作用の実験的研究』と『現代治療学入門(1892年)』をまとめている。Th.リチャード・フレイサー卿(1841-1920年)はカルカッタ生まれで、ストロファンツスの薬力学と毒物学を研究する専門家である。もう一人のスコットランド出身のアーサー・ロバートソン・カーシー(1866-1926年)はシュミーデバーグの門弟で、薬理学の手引書に関心を寄せただけでなく、ジギタリス、光学異性体の拮抗作用、尿排泄の生理学など重要な研究を行った著作家である。
フランス医学は相対的に遅れて、薬理学と臨床治療学の分離がはじまった。トロシューはまだ、「薬で治れば、薬が治す方法は問題ではなかろう」と疑問を投げかけていた。何とマジャンディーとCl.ベルナールのお手本は、母国では数冊の精神力学課程『パリ医学部の毒物・薬の生理作用に関する講義』の作家ブラウン・セカートとフリック・アルフレッド・バルピアン以外は、ほとんど引きつぐ者がいなかった。19世紀の後半と20世紀初頭10年に、フランスでは独創的で有名な治療者が何人か現われている。アコニチン、臭化カリウム、カラバル豆、抱水クロラール、クラーレ、シンコニンなどの臨床薬理学と実験薬理学を研究し、『治療学雑誌』の創刊者だったアドルフィー・ギュベール(1821-1879年)。 有名な『治療辞典(1892年)』の作者でリンとアルコールの作用を研究したジュラルディン・ビューメツ(1833年、バルセロナ1895年)。 P.J.M.ドルビュー(1851-1938年)。 アン・ガブリエル・ポーシュー(1851-1938年)。配糖体に関する貴重な研究をしたエミール・ボケール(1851-1921年)。
しかし、20世紀初頭10年のフランス薬理学で、真の光はドイツのE.フィッシャーとヴィル・スタータの弟子エルンスト・フォーニュー(1872-1949年)である。彼は1911年以降、パスツール研究所化学療法部を指揮している。この後の本文で彼の業績の主な部分について述べる予定である。
北アメリカの薬理学も19世紀末には重要な位置を占めていた。ジェームス・ブラック(1815−1893年)ではじまり、ホラチオ
C・ウッド(1841-1920年)が育て、ジョン・ジェイコブ・アベル(1857-1938年)により完成したといえるだろう。ウッドは亜硝酸アミル、ヒヨスチン、アトロピンの薬力学の研究者で、アベルは副交換神経髄質の活性塩基を単離してエピネフリンと称し、インスリンの結晶化、ヒスタミンの生物作用の知識に寄与し、トラルド・サルモン(1874年生れ)と一緒に、私たちが調査中の時代の終わりには、国際的な指導者として認められるようになった。
イタリアの薬理学者では、パドアで優れた薬理研究所を創設したルイジ・スカレンジオ(1797-1869年)、フェルディナンド・コレッティー(1819-1881年)、ジゼッペ・オロシ(1816-1875年)、ピエトロ・ギャコーサ(1853-1928年)、ピオ・マルフォーリ(1861年生れ)である。
スペインの治療者もとりあげる価値がある。ヴィンセント・アスエロ(1807-1873年)、ベニト・ベルナルド(1845-1816年)、ヴィンセント・ペセト(1858-1945年)がいる。しかし、本格的な薬理学の研究は、テオフィロ・エルナンド(1881-1976年)の門弟たちの仕事からはじまった。
この10年間に薬物療法で使った自然ないし半自然の薬のなかに特記すべき薬がある。ピロカルピン(ハーディー、1871年:コーチンとウェーバー、1874-1976年)、コカイン(1850年にナイマンが抽出、1858年にV.K.アンレプが、1884年にC.ケーラー)、ストロファンツス(T.R.フレーザー、1904年)。 ストロファンチン(A.フランケル、1905年)、ヘロイン(ドレーサー、1896年)、ノボカイン(アインホルン、1925年)、エルゴトキシン(バーガーとダニエル:クラフト、1906年)、パントフォン(アーフリー、1909年)、副腎髄質の活性塩基(粗製油抽出物G.オリバーとS.A.シェファー、1985年)、エピネフリン(マーベル、1908年)、スプラレニン(フォン・フォート、1901年;結晶アドレナリン、高峰、1901年)。
合 成 薬 に よ る 化 学 療 法
ウェーラーが正式に製造した合成薬は、有機物が実験室で製造できることを証明した。しかしその後、化学の発達がもう一つの重要な事実を明らかにした。人類は合成によって自然界にまったく存在しない物質、すなわち天然物には絶対にない作用や非常に珍しい作用をもつ物質を手に入れることができた。自然の模倣者でその競争相手である化学は、ディデロートによれば実際、自然を超えはじめた。薬の広大な分野がこのようにして生れている。
1832年にリービッヒが合成した抱水クロラールは、1869年にリーブライヒにより催眠薬や麻酔剤として医療の場に登場し、新しい治療法の第一歩を踏だした。その後まもなく(1882年)シュミーデバーグとセルベッロは、この催眠剤をパラアルデヒドと併用する方法をつづけ、それからも同じように1885年にシュミーデバーグ自身がデュマスにより1835年に合成されたカルバミン酸エーテルのエチルウレタンを、バウマンが1885年に合成スルフォナールを、1888年にバウマンとカーストがトリオナール(メチスルフォナール)を、E.フィッシャーとフォン・メーリングが1903年にベロナール(ジエチルバルビツール酸)を、1905年にプロポナール(ジプロピルバビツール酸)を、ホールラインが1911年に催眠剤のフェニルバルビツール酸(ルミナール)など、そして今日まで多数の人々が薬を開発している。
催眠薬に平行して2種の接線がある。サリチル酸療法ともう一つが解熱鎮痛剤療法である。第一の線はサリチル酸(コルベとローテマン、1860-1874年)で、以下サラゾピリン(リーデル、1884年)、ザロールまたはサリチル酸フェニル(M.フォン・ネンキ、1885年;2種の物質が会合した合成物で胃液の酸性や腸液のアルカリ性で分離する「ネンキの原理」)、アスピリン(アセチルサリチル酸の合成、ゲルハルト、1833年;治療への応用はドレーサー、1899年;アスピリンの名称で普及、1902年)が連続した輪となっている。第二の方向はアンチピリン(E.フィッシャー、クノール、フィレーネ、1884年)、フェナセチン(カスト、O.ヒンベルグ、1884年)、アセトアニリド(コーヘン、ヘップ、1886年)、ピラミドン(1894-1904年)である。化学療法剤合成の第3番目の軌跡は、フォーニュー(1904年)による局所麻酔剤エストバイン(勝手な命名で英語のstove、スペイン語でhorno、フランス語のfourneau:かまどの意味)の成功である。
合成化学療法の歴史上および治療上の重要性については、すでに述べてきた通りである。一方、医師は自然が創りだすよりも有効な薬、つまり実際に聞いたことがないような治療効果をもつ薬を使用することができた。他方で科学的に薬の分子構造と生体内の治療効果の関係(シュミーデバーグの言葉では構成成分や付加物と説明)をみつけることが可能となった。このため必要に応じ構造を変えて(アミノ化、アセチル化など)、有効な薬の研究が実験室で行うことができた。しかし、全体的に考えると19世紀末と今世紀初頭数年の精密で豊富な合成化学薬は、対症療法的な催眠剤、鎮痛剤、解熱剤などの新薬の開発にとどまっていた。対症療法的な化学療法剤の治療から、原因療法的な化学療法に進歩しなければならなかった。20世紀になってまもなく、当時の医学会に偉大な人物ポール・エールリッヒが登場した。詳細に調べてみよう。
実 験 治 療 学 と 病 因 に も と づ く 化 学 療 法
前の二節で述べたシュミーデバーグを主体とした実験薬理学と、合成薬による化学療法の第一歩で、1900年から1905年の科学的薬理学が指向した概念が明快になった。それ以来、薬物療法の新時代はフランクフルトのゲオルグ・シュペーヤー・ハウスでスタートをきり、下記の大きな特徴をもつに至ったようだ。シュミーデバーグが分析薬理学の対極にある実験薬理学を宣言したことと、これまでの対症療法とはまったく異質な病因を標的とした化学療法は大きな勝利であった。こうした発展の意義と構造を完全に評価するには、すばらしい創始者ポール・エールリッヒ(1854-1915)を知らなくてはならない。
エールリッヒの多大な業績は多方面にわたり、組織学、血液学、癌種学、生理病理学(ジアゾ反応)、細菌学、免疫学におよんでいる。しかし、彼の業績で最大の進歩は化学療法の研究と、実験治療学を開拓したことである。この二つ業績には、1905年以前にエールリッヒが取り組んだ仕事とその考察という必要条件が不可欠であった。もっとも重要な事項は下記の通りである。
1.対症療法でなく、病因を対象とした化学療法に先行する研究。エールリッヒがゲオルグ・シュペーヤー・ハウスで実施した方法より以前の化学療法には、水銀を駆梅剤として使う古い方法をのぞき、つぎのようなものがあった。1886年にウンナが皮膚科領域でイヒチオールとレゾルシンをはじめて治療に使用。コッホが塩化第二水銀を実験。1906年にビーブリッヒがスカーレット・レッドを治療に導入。1860年にラベランとコッホがビーシャンでえたアトキシルをトリパノゾーマ症の治療に適用。こうした専門家たちの知識にもかかわらず、パラケルススの「生命力」と「特定薬」といった旧式の観念が実験では有用であった。医師が疾病を阻止したり撲滅する目的で、それぞれ特定薬を使うには各々の病因が必要である。
2.当時では最新の抗ジフテリア免疫治療法を使った治療学の成功例(免疫療法の支援を受けた)。
エールリッヒの免疫学時代は、コッホではじまりその後、実験治療学研究所に移るが、彼の関心はこうした精力的な活動に向けられた。エールリッヒの「側鎖説」と「薬の化学構造および生理作用の関係」の強い類似性について長々と論ずる必要はないだろう。
3.薬の目標(患者が実際に治癒すること)に関して、ブッヒハイムとシュミーデバーグが行った実験薬理学では不十分であると確認。薬理学では健常動物とそれから採取した組織を使う。伝統薬の生物作用や多くものは、対症的な効果を有する新薬の活性研究に限定されていた。こうした状況に接して新しい専門分野、すなわち実験治療学を創る必要があった。この分野では、治療の対象者と同じ疾病に罹患し同じ病因をもった動物に有効な薬を投与して実験した。エールリッヒが後年はっきりといっているように、下記の二つの科学研究が青年時代の彼に強い印象を与えた。E.ホイベルの鉛中毒(鉛中毒の病因と症候、1871年)とストリキニーネの化学的修飾およびその薬理学的性質に関する研究である。ホイベルは鉛中毒で死んだ動物の臓器を慎重に分析し、鉛の所在を測定した。それから健常動物を殺し、内蔵をとりだして薄く剥がし、鉛塩液中に浸した。化学分析で鉛が中毒に侵された臓器とまったっく同じ場所に蓄積していることを証明した。鉛が残留する原因は臓器固有の化学性である。1859年にシュタールシュミットがストリキニーネをメチル化して、テタニーを起こす薬を治療用の薬に変える発見をした。この発見によりその後、ストリキニーネに関するフレーザーとブラウンの困難な研究(1868-1870)や遊離アンモニアを使用して相対的に無害なクリンをクラーレよりも毒性が強いクラリンに変えたボームの研究も生まれた。
エールリッヒのこうした初期の三つの発見で前進したのは、組織染色という独創的な活動領域であった。彼は1890年頃にメチレン・ブルーの親神経性に関する生化学問題に厳しく対処していたが、皮肉を込めて「私は医学の染色家以外の何ものでもない」と語っている。メチレン・ブルーがなぜ神経を染色するか、神経がなぜメチレン・ブルーで染色されるか、これがエールリッヒの研究主題であった。第一の問題でこの染色剤の生物学的性質と染色性を検討し、イオウの役割を発見することができた。第二の問題はオーバートンとメイヤーが製造した全身麻酔剤に関して、親神経性と親脂肪性を一致させた。その後、同じ考え方を免疫治療学に応用し側鎖説を創りあげようとした。1905年以降、ゲオルグ・シュペーヤー・ハウスの指導者として、化学療法の治療問題に携わり実験治療学の計画を完成させた。エールリッヒの化学観、疾病の病因学、生理病理学、有効な治療に対する考え方とともに、こうした諸家の化学知識が二つの労作に共通する核となっていた。エールリッヒはベンゼン環や化学式が目に浮かんだに違いない。この優れた化学観からアトキシル(パラアミノフェニルアルシン酸)の構造と殺スピロヘータ作用の研究がはじまった。シャウテインが梅毒を誘発する梅毒トレポネーマを発見し(1905年)、ワッセルマンがその生物学的診断法(1906年)をみつけ、ロークスとメチニコフが人の梅毒が実験で猿に伝染することを証明した。トリパノゾーマと梅毒の間では多くの類似点がある。アトキシルはニワトリ・スピロヘータ症と睡眠病の治療に有効である。エールリッヒは日本の細菌学者の志賀と秦および化学者ベルテイムの協力をえて、本来は寄生虫用薬のアトキシルを病原菌に毒性をもち、臓器親和性が最小で、宿主の患者に無害な薬に変換させる研究をスタートさせた。研究事業の主たるステップはつぎのようであった。
a)これまでの誤ったデータとは逆に、アトキシル(フェニルアルシン酸のアミノ誘導体)の真の化学構造を確立。
b)アルサニルのアセチル化および有効な駆梅剤アルサセチン(A.ナイセル)の獲得。 しかし、この殺寄生虫剤の服用は視神経障害を誘発する。
c)アルサニリン酸とアルサセチンはともに試験官内でトリパノゾーマに無効で、各分子が治療効果を発揮するには、体内で変化しなければならない。
d)作用仮説:アルサニリン酸とアルサセチンの修飾は、動物組織の化学変化で起こりえるし、そうでなければならない。
e)前記二つの実験的な化学変化でできた物質が寄生虫に対して毒性があり、宿主に無害なことを立証(したがって、アルセノフェニルグリシンが誕生し、その駆梅作用がナイセルによって確立された)。
f)トリパノゾーマ細胞にアルセン受容体と酢酸受容体があり、トレポネーマ細胞にはアルセン受容体、ハロゲン受容体、水酸基受容体があると証明。
g)分子内にアルセノベンゼンに関連する水酸基を有する薬の系統的研究。
h)親寄生虫性で臓器非指向性の条件を満たす、ジオキシジアミノアルセノベンゼンの発見(アルセノグリシンはエールリッヒが行った実験の418番目の薬)。ジオキシジアミドアルセノベンゼンは606番目で1910年に登場。 サルバルサンの名称で有名。
i)駆梅剤の標準的投与法を確立するために、臨床で論理的に慎重に確認。
j)サルバルサンとホルムアルデヒド・スルフォキシルナトリウムを配合した ネオサルバルサン(914番)の獲得。最初のサルバルサンより使いやすい (1912年)。
この才能豊かで辛抱強い研究者が、血管に薬を注射して患者の組織を損傷せずに、病原菌を撲滅するという目標を達成した。この薬はエールリッヒの有名な説明のように「魔法の弾丸」に変った。エールリッヒの研究に関する二つの「合い言葉」のうち、一つは「結合せざれば反応なし」である。もう一つの重要な言葉は「優れた殺菌療法」で、この獲得は十分に達成された。ポール・エールリッヒによる新薬の普及とその名声はなんら驚くにあたらない。当然のことだろう。偉大な薬理学者の業績は、抗生物質の発見という輝かしい時代とサルバルサンで梅毒を治療しない現代であっても、なお明るく光を放っている。
|